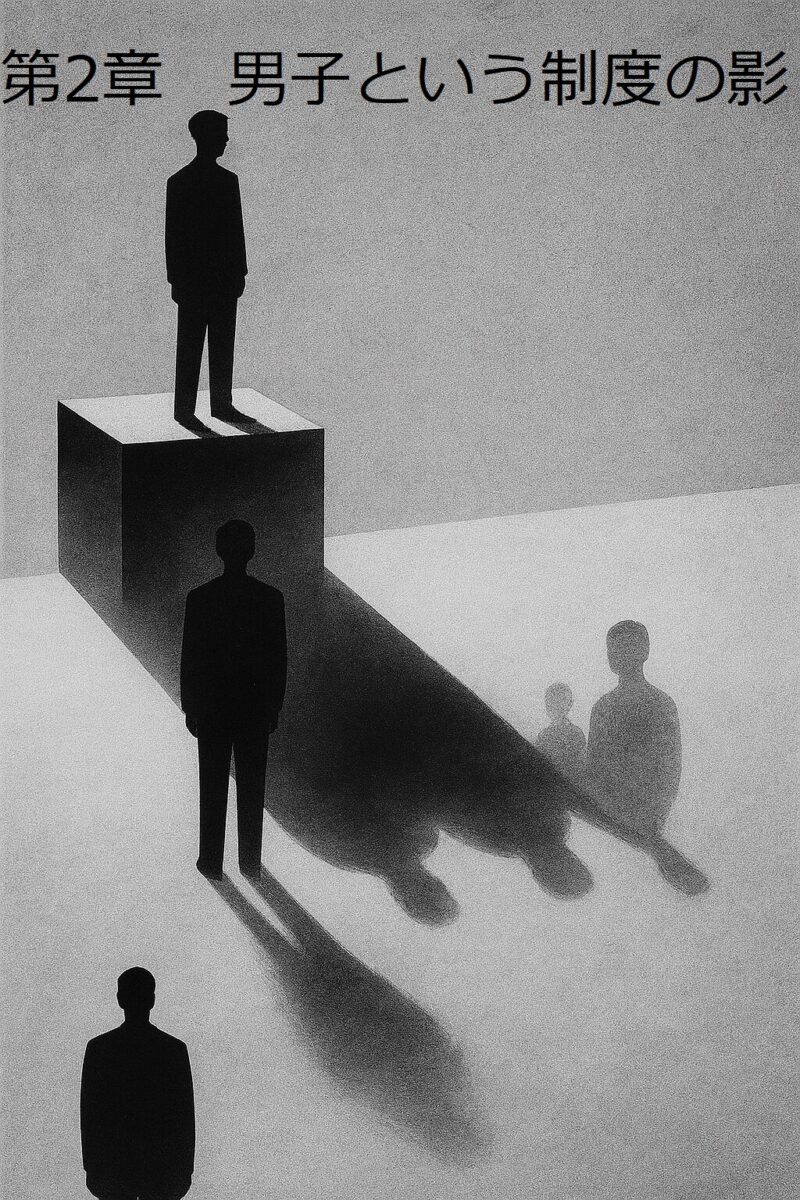こんにちは、\イッカクです/
今回は、「象徴再構成論──男系男子を超えて」シリーズ2回めです。
📘 第2章:男子という制度の影
あなたは、「男子」という言葉に、制度の影を感じたことがありますか。
それは、血統の語彙として語られます。
継承の条件として記されます。
けれど、その言葉が象徴を定義する瞬間、誰かが排除されていませんか。
制度は語ります。
「皇位は、男系の男子がこれを継承する。」──皇室典範第1条。
その語りは、伝統と安定を装っています。
けれど、あなたはその言葉に、象徴の広がりを感じましたか。
むしろ、象徴が制度の中で狭められていくように感じませんでしたか。
男子という語は、制度の中で光を浴びています。
だが、その光が照らすのは、誰かの不在です。
その「誰か」とは、象徴を支えるはずの国民です。
憲法は語ります。
「天皇は、日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴である。」──憲法第1条。
この語りは、象徴が国民と結びついていることを示しているように見えます。
けれど、継承の条件に国民の姿はありません。
皇室典範は「男系男子」と語るだけで、国民の参与を語らない。
象徴の定義に国民が含まれていても、継承の条件には含まれていない。
その構造こそが、象徴の制度的影を生むのです。
象徴の定義は憲法が語り、
継承の条件は皇室典範が語る── この分業構造こそが、
象徴の排除構造を生む源泉なのです。
あなたは、制度の条文を読んだことがありますか。
憲法第1条と皇室典範第1条。
そこに記された語彙の間に、
象徴の実感はありますか。
それとも、制度が象徴を血統に閉じ込めているように感じますか。
「男系」とは、父から子へと続く血の線を意味します。
「男子」とは、その線上に立つ性別の条件です。
この二重の語彙が、象徴の継承を制度の中で囲い込みます。
そしてその囲いの外に、語られない者たちが立ち尽くすのです。
「私は、象徴を継ぐ資格がない。
なぜなら、私は男子ではないから。」
この言葉に、制度は答えません。
制度は、継承資格を定めることはできても、
象徴の意味を問うことはできないのです。
あなたは、象徴を制度の中に見出せますか。
それとも、制度の外側に立つ者の沈黙の中に、
象徴の気配を感じますか。
「私は、象徴を見たことがない。
だが、象徴に見られている気がする。」
この言葉が意味を持つのは、
象徴が制度の語りを超えて、
私たちの視線の中に、あるいは視線の外に、存在しているからです。
制度は、語ることで象徴を囲い込もうとします。
けれど、語られた瞬間に象徴は逃げ出す。
「男系男子」という語が制度の中で繰り返されるたびに、
象徴はその語の外へと、静かに後退していくのです。
あなたは、その後退の気配を感じたことがありますか。
制度が語れば語るほど、
象徴が遠ざかっていくという逆説を。
この章は、「男子」という語が制度の中で
象徴を狭めていく構造を描く章です。
そしてその構造を、あなたの問いによって揺さぶる章でもあります。