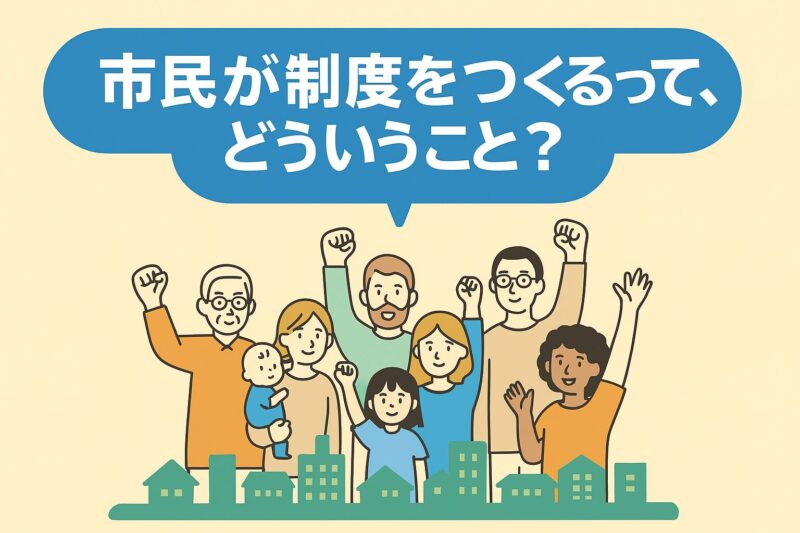市民が制度をつくるって、どういうこと?
こんにちは、\イッカクです/
前回、「制度って誰のためにあるんだろう?」
という話をしました。
今回はもう少し踏み込んで、
「市民が制度をつくるって、どういうこと?」
について考えてみたいと思います。
制度って聞くと、
なんだか遠い世界の話に感じるかもしれません。
政治家や官僚が会議室で決めているもの。
テレビのニュースでしか見ないもの。
そんなイメージを持っている人も多いと思います。
でも、実は制度って、
私たちの暮らしのすぐそばにあるんです。
たとえば、保育園の待機児童。
年金の仕組み。
災害が起きたときの支援体制。
学校の給食費の無償化。
これらは全部「制度」の話です。
そして、こうした制度がどう設計されるかによって、
私たちの生活の質が大きく左右されます。
制度がうまく機能すれば、安心して暮らせる。
でも、制度がズレていたり、
誰かの都合で歪められていたら、
そのしわ寄せは、いつも庶民にやってきます。
じゃあ、制度って誰がつくっているのか。
国会議員?
官僚?
専門家?
もちろん、そういう人たちが関わっているのは事実です。
でもね、制度って、本来は「みんなのもの」なんです。
暮らしの中で「こうした方がいい」と感じること、
「この仕組みはおかしい」と思うこと、
そういう声が集まって、
制度が見直されたり、
つくられたりするのが本来の姿なんです。
たとえば、
地域の人たちが「子育て支援が足りない」と
声を上げて、 自治体が新しい制度をつくったり、
予算をつけたりする。
それも立派な「市民による制度づくり」です。
でも現実には、制度って
「上から降ってくるもの」や
「わたしたちが知らない間に決まって」しまっている。
そう、知らないうちに決まっていて、
気づいたら「こうなりました」と言われる。
それじゃあ、納得できないですよね。
制度って、暮らしの中から生まれるべきものなんです。
机の上でつくられるものじゃなくて、
現場の声、
生活の実感、
地域の知恵から育っていくものなんです。
たとえば、
保育園の送り迎えが大変だという声があれば、
送迎バスの制度を検討する。
高齢者が病院に通いづらいという声があれば、
移動支援の制度を整える。
そうやって、制度は「声」から生まれるんです。
なので、たとえば
県知事が、県民と十分に話し合いや意識合わせを行わずに
一方的に、イスラム文化の人たちを就労させて、結局
「移民」させるために、土葬の環境整備までやろうとしていますが
県民の間では、疑念が広がっており、移民制度は県民にとって
受け入れられないものとなっています。
このように、庶民の「声」が届かない社会では、
制度はどんどん現実から離れていきます。
そして、誰かの都合でつくられた制度が、
市民の暮らしを縛るものになってしまう。
だからこそ、
制度を「市民がつくる」という感覚を
取り戻すことが大事なんです。
もちろん、いきなり法律を書いたり、
予算を組んだりするのは難しい。
でも、
「こういう制度が必要だ」とか
「この制度のココがダメだ」とか
「制度を確定する以前に、なぜ県民の意志を確かめなかったのか?」とか
言葉にすることは、
誰にでもできます。
ソレは、、、
SNSで発信する。
地域の集まりで話す。
ブログに書く。
それだけでも、制度づくりや
制度への修正意見や
あるいは、制度そのものの可否意見
の一歩になります。
制度って、
専門家だけのものじゃないのです。
むしろ専門家は最近、
無頓着で制度を
無理やりつくる傾向にあります。
だから、市民が関わってこそ、
ほんとうに暮らしに根ざした制度になるんです。
そしてもうひとつ大事なのは、
「納得できる制度は、参加から生まれる」ということ。
誰かが勝手に決めた制度よりも、
みんなで話し合って、
意見を出し合って、つくった制度の方が、
ずっと納得できるし、守ろうという気持ちにもなります。
制度は、暮らしの中から生まれる。
そして、暮らしの中で育てていくものなんです。
それは、
政治家だけに任せておくものじゃない。
私たち一人ひとりが、「制度の担い手」なんです。
たとえば、町内会での防災訓練。
地域の子育てサロン。
学校の給食に関する保護者アンケート。
こうした小さな場面にも、
制度の芽があるんです。
「こうした方がいい」と思ったら、声にする。
「この仕組みはおかしい」と感じたら、仲間と話す。
その積み重ねが、制度を育てる力になります。
制度は、誰かが勝手につくるものじゃない。
みんなで考えて、みんなで育てていくものなんです。
次回は、
「制度は誰に仕えているのか?」というテーマで、
制度が本当に守っているのは誰なのか、
支配と参加の違いについて考えてみたいと思います。
読んでくれて、ありがとうございます。
一緒に、制度のこと、考えていきましょう。🙏