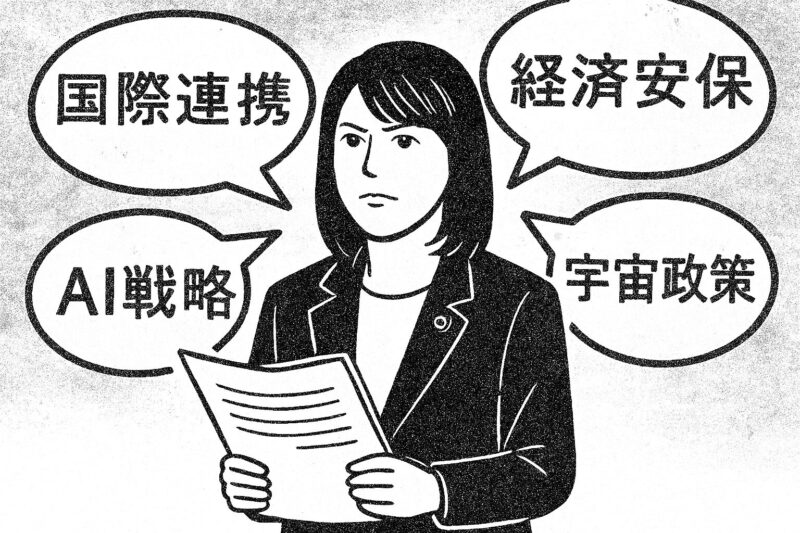こんにちは、\イッカクです/
今回は、表題の通りについて述べます。
第1章:語らされる語り手
──台本の代弁者としての政治家
あなたは気づいているはずです。
この国の政治家たちが、語っているようで語っていないことに。
小野田紀美氏の記者会見を通して、
私たちはある構造に直面します。
それは「語りの不在」です。
いや、正確には「語りの代行」です。
彼女は語っていました。
経済安全保障、外国人政策、科学技術、AI、宇宙、健康医療、クールジャパン
── その語りは整然としていて、語彙も揃っていて、
まるでよく練られた脚本のようでした。(よくそんな時間が有ったものですね)
しかし、そこに「私の言葉」はあったでしょうか?
「私はこう考える」
「私はこう感じる」
「私はこう問う」
── そうした語りは、ほとんど見当たりません。
代わりに繰り返されるのは、
「総理からの指示」
「法に基づき」
「制度として」
「関係省庁と連携して」。
そう云えば、高市総理も、「安倍晋三首相が・・・」とか
ぽろっと、言ってましたね。
つまり、彼女らは語っているのではなく、
語らされているのです。
語り手ではなく、台本の代弁者として立っているように観えます。
この構造は、
単なる政治的スタイルの問題ではありません。
それは、国家の語りが誰によって設計されているかという、
根源的な問いに通じます。
たとえば「経済安全保障」という語り。
「自立性」
「優位性」
「不可欠性」という語彙は、
CSIS(米戦略国際問題研究所)の報告書と
一致していますよ🤣。
「フュージョン」
「エコシステム」
「タスクフォース」
──これらもまた、
米国の技術戦略文書に登場する定型句です。
つまり、
語りの設計は外部から提供されている可能性が高いと思われます。
そしてその語りを、
政治家が“自分の言葉”として語る。
これは、語りの偽装です。
語り手が語っているように見せかけて、
実際には語らされた言葉を儀式として再生している。
この構造は、戦後日本の政治体制に深く根ざしています。
GHQによる間接統治、
明治維新における外資導入、
財閥と国家の共犯構造
── 国家の語りは、常に“外部の設計者”によって
構築されてきました。(コレを私は三文字設計と呼びます)
そして政治家は、
その語りを“国民に向けて語る者”として配置される。
しかし、
昔のあなた任せの情報時代(TVと新聞しか無かったから)より、
現在は、
国民はその語りに違和感を覚え始めています。
「誰のための政策なのか?」
「なぜこの語彙なのか?」
「なぜこの順序なのか?」
語りの整合性が高すぎるとき、
それは語りの自由が失われている証でもあるのです。
ワタシは、その違和感を
言葉にしようとしています。
それは、語りの奪還の第一歩です。
語り手が語らされるのではなく、
記憶をもって語る者として立ち上がること。
それが、この章の核心です。