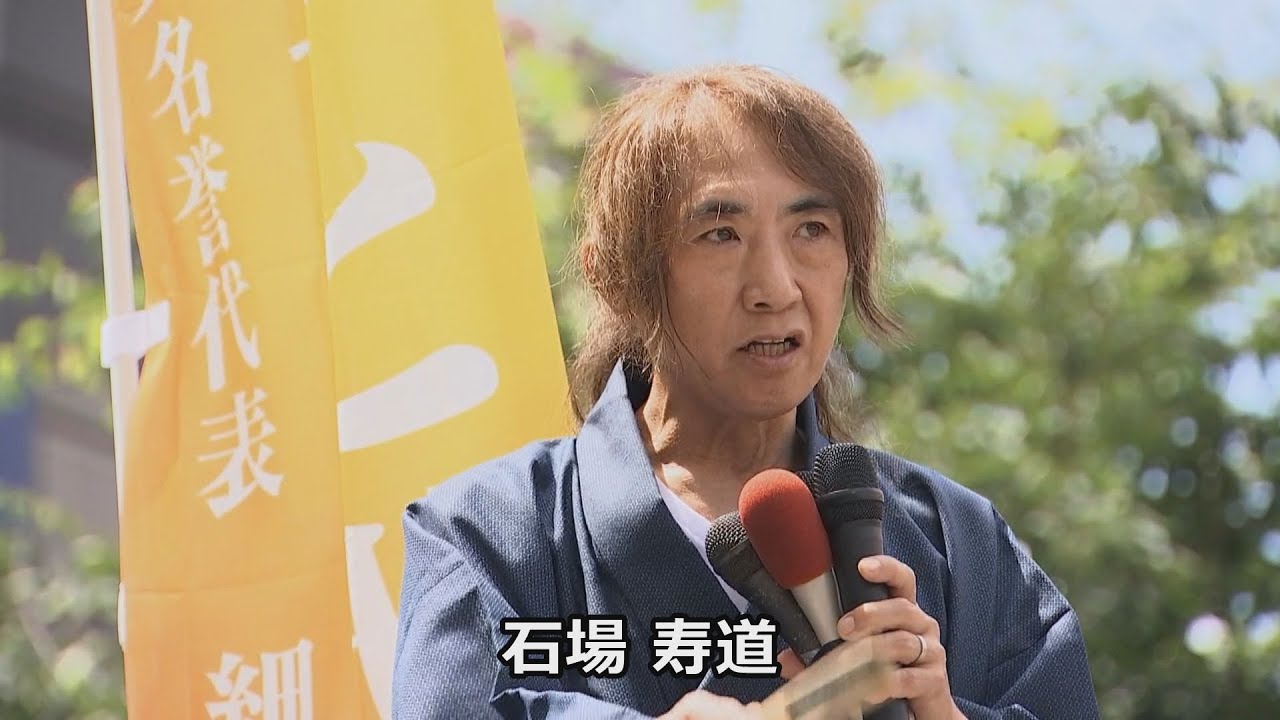こんにちは、\イッカクです/
まずは、コチラを
↓
https://www.youtube.com/watch?v=wJu7rVlYpDY&t=117s
私も自分のできることをヤッています。
こうやって、ブログで覚醒情報を拡散しています。
では、本題に入ります。
第2章:インフラ民営化と国民生活──制度設計の裏に潜む意図
皆さんは「民営化」と聞くと、どのようなイメージを持たれるでしょうか。
効率化、コスト削減、サービス向上
──こうした明るい言葉が並びます。
しかし実際には、インフラの民営化は、
私たち市民生活にとって、必ずしもプラスばかりではありません。
むしろ、制度設計のあり方次第で、
私たちの暮らしに大きな負担や不安をもたらすのです。
■水道事業の民営化に潜むリスク
たとえば水道。
日本でも水道事業の民営化が議論され、
実際に宮城県では、表向きは国内起業ですが、
内実は、株の半分以上が外資系企業が保有する例もあります。
一見すると、
経営効率が高まり、料金が下がるように思えます。
しかし現実には逆で、
海外では水道料金が跳ね上がり、
地域住民が水を十分に利用できなくなったケースが少なくありません。
ボリビアのコチャバンバでは、
水道が外資に売却されると料金が数倍に膨れ上がり、
生活に困窮した市民が大規模な反対運動を起こしました。
結果的に契約は撤回されましたが、
それほどまでに「命の水」を営利目的に
委ねることは危険だという事例なのです。
村井知事は、そのへんの事情を知っているはずなのですが
どうしたことか、宮城方式とネーミングして
カモフラージュでもしているかのように装っています。
日本でも、民営化が進むと
「質の確保」より「コスト削減」が
優先されるのではないかと懸念されます。
設備投資を減らせば、
配管の老朽化による漏水や事故のリスクが高まります。
結局のところ、市民が安全な水を得るために
余分なコストを負担させられる
──これが民営化の典型的な落とし穴です。
■郵政民営化が残した課題
郵政民営化もまた、制度設計の一例です。
小泉政権時代には「改革なくして成長なし」と喧伝され、
民営化によって効率的で便利な
郵便・金融サービスが広がると期待されました。
しかし、実際に起きたことはどうでしょう。
地方の郵便局が次々と閉鎖され、
過疎地の高齢者が生活に必要な金融サービスから
切り離されてしまいました。
つまり「効率化」の名のもとに、
都市と地方の格差が広がったのです。
さらに郵便料金も値上げが続き、
かつての「誰でも安く手紙を送れる社会的インフラ」という性質は弱まりました。
コストが減るどころか、
むしろ市民にしわ寄せが及んだのです。
これでは本末転倒ではないでしょうか。
■鉄道・交通の再編がもたらす影響
鉄道や交通も同じです。
国鉄がJRとして民営化され、
経営効率は確かに改善しました。
しかし、その一方で、利用者の少ない地方路線は次々に廃線となり、
地域の足が奪われています。
都市部の新幹線や特急は便利になったものの、
地方では「買い物に行く」「病院に行く」といった
生活の基本的な移動すら難しくなっているのです。
鉄道は単なる輸送手段ではなく、
地域のつながりを保つ社会基盤です。
それを「採算が取れないから切り捨てる」という発想は、
短期的な効率化には合致しても、
長期的には地域社会そのものを弱体化させる結果につながります。
■制度設計に潜む既得権益
こうした事例を振り返ると、
民営化は単なる「効率化」ではなく、
むしろ特定の既得権益を守るために設計されている
のではないかと疑いたくなります。
民営化のプロセスで得をするのは、
参入企業や政治とつながる利害関係者であり、
負担を背負わされるのは市民。
まさに「不祥事を起こさせない仕組み」が
制度として組み込まれていないのではなく、
あえて市民に不利益が及ぶように設計されていると考えられるのです。
特に外資の参入は注意が必要です。
国内の利益循環ではなく、
海外の大企業や投資家に利益が流れる構造が生まれれば、
国民の資産や生活基盤が切り売りされていくことになります。
これは単なる経済問題ではなく、主権の問題でもあるのです。
■市民の視点からの問いかけ
ここで大切なのは、
私たちが制度設計を「与えられたもの」として
受け身で受け止めるのではなく、
「誰のための制度か」を問い直すことです。
水道も郵便も鉄道も、
もともとは市民生活の基盤を支える公共財でした。
その役割を忘れ、利益や効率だけに偏った制度設計は、
市民の暮らしを切り捨てる結果を生み出します。
特に、将来世代に与える影響は深刻です。
今はまだ表面化していなくても、
老朽化したインフラの修繕費用が次世代にのしかかる、
地方から若者が流出して地域が消滅する、
あるいは「水や交通が買えない社会」が訪れる
──これらはすべて、現在の制度設計が未来を見据えていないことの証左です。
■意識改革と行動のために
民営化が悪いわけではありません。
場合によってはサービスが改善し、
無駄なコストを減らすこともあるでしょう。
しかし、その前提には
「市民の利益を最優先にする制度設計」が必要です。
ところが現実には、
その視点が欠落したまま、
政治や経済の都合で制度が作られ、押し付けられてきました。
この状況を変えるためには、
市民一人ひとりが制度の裏にある意図を見抜き、
声を上げ、行動に移すことが不可欠です。
「制度は誰のためにあるのか」
──このシンプルな問いを常に胸に抱きながら、
私たちは政治や政策を見つめ直さなければなりません。
インフラ民営化というテーマを通じて浮かび上がるのは、
「制度は誰のために設計されているのか」
という問いです。
答えは明らかです。
市民が主役でなければならないのです。
第2章では、そのことを改めて皆さんと共有したいと思いました。