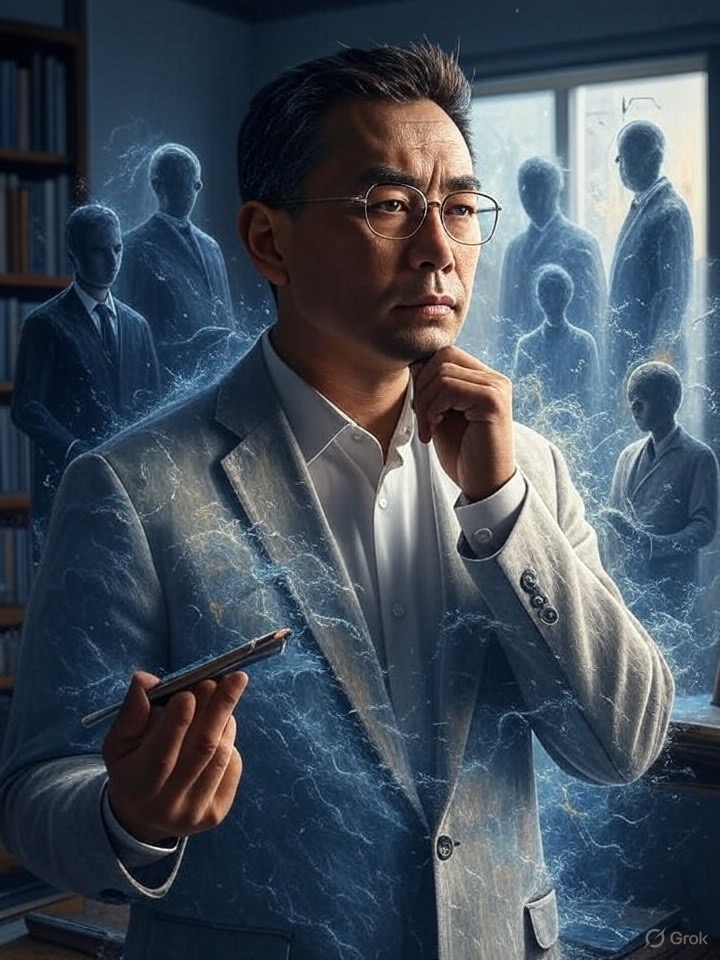第1章:制度は誰が守るのか──市民の認知に語りかける論考の意義
■制度は「誰かが守るもの」ではない
制度って、どこか遠い存在に感じませんか? 行政が作って、専門家が運用して、政治家が調整する──そんなふうに思っている人が多いかもしれません。 でもね、実はそうじゃないんです。 制度は、私たちの生活そのもの。 水道の蛇口をひねれば水が出る。 子どもが学校に通える。 病院で診察を受けられる。 これらはすべて、制度の働きによって成り立っています。 そして、その制度が壊れれば、私たちの生活も壊れてしまう。 それなのに、制度の設計や防衛に市民が関与する機会は、驚くほど少ないんです。 多くの人が「制度は与えられるもの」として、ただ受け取っているだけ。 この受け身の姿勢が、制度の隙間を生み、悪意ある介入を許してしまうんですよ。
■制度の防衛者は誰なのか
じゃあ、制度を守るのは誰なんでしょう? 行政?専門家?政治家? もちろん、彼らにも責任はあります。 でもね、制度の最終的な受益者は、私たち市民一人ひとりなんです。 だからこそ、制度の防衛にも市民が主役として関わるべきなんです。 この論考は、その視点をあなたに届けたい。 制度の危機は、派手な事件として現れるわけじゃありません。 静かに、巧妙に、文化や情報、資本の流れの中に紛れて、じわじわと侵食されていく。 たとえば、水源地が外国資本に買収される。 宗教施設が土地を囲い込む。 行政の盲点を突いた土地取引が進む。 これらはすべて、制度の隙間を突いた「制度戦」なんです。 そして、その戦いはもう始まっている。
■認知の転換が制度防衛の起点になる
この制度戦に立ち向かうには、まず市民の認知を変える必要があります。 制度は「誰かが守るもの」じゃない。 「自分たちが守るもの」なんです。 この認識の転換がなければ、制度の防衛は空中戦に終わってしまう。 この論考は、素材をただ投げるだけのものではありません。 行政に拾ってもらうことを期待するものでもない。 むしろ、市民一人ひとりの認知に語りかけて、危機を「自分ごと」として捉えてもらうための言語的装置なんです。 制度の防衛とは、倫理的な抵抗であり、知的な連携です。 怒りや恐怖ではなく、冷静な構造分析と歴史的文脈の理解が支えになります。 この論考は、そうした市民の知的防衛戦を支えるための素材であり、共通言語なんです。
■次章への予告──制度戦の三層構造を可視化する
次の章では、制度がどのように侵食されるのか──そのメカニズムを「情報戦」「制度戦」「文化戦」の三層構造として整理して、具体的な事例とともに見ていきます。 市民が制度の設計者であり、防衛者であるという視点を、さらに深めていきましょう。