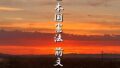こんにちは、\イッカクです/
今回は、下記の問いに対する一つの解です。
どの現象がどの I に偏っているか
提示された「3i/ATLAS」の理論的枠組みに基づくと、
三つの「I」はそれぞれ、
アナログ的な現実の特定の側面を捉え、処理する機能に偏っています。
三つの「I」はそれぞれ、
アナログ的な現実の特定の側面を捉え、処理する機能に偏っています。
これは、デジタル化によって切り捨てられる
「連続性」「揺らぎ」「位相」といった
要素を扱うために設計された、
人類のアナログの知の基盤を構成します。
「連続性」「揺らぎ」「位相」といった
要素を扱うために設計された、
人類のアナログの知の基盤を構成します。
以下に、どの現象や対象がどの「I」に偏っているか、
あるいはその「I」の機能の中核であるかを解説します。
あるいはその「I」の機能の中核であるかを解説します。
1. 情報 (Information) に偏っている現象
「情報(Information)」は、
現実世界を連続量として捉える機能に偏っています。
デジタル的な符号化や離散化によって
切り刻まれる前の、
原初の情報形態が対象となります。
現実世界を連続量として捉える機能に偏っています。
デジタル的な符号化や離散化によって
切り刻まれる前の、
原初の情報形態が対象となります。
• 連続量としての情報の受信。
• 情報が持つ波形(Waveform)。
• 情報が持つ密度(Density)。
• 情報が持つ位相(Phase)。
この「I」は、人間の感覚器官が
光の強弱や音の波形を
連続的に受け止める、
そのアナログ受信機としての機能に対応しています。
光の強弱や音の波形を
連続的に受け止める、
そのアナログ受信機としての機能に対応しています。
2. 直観 (Intuition) に偏っている現象
「直観(Intuition)」は、
変化し続けるアナログ的な「揺らぎ」を感知し、
処理する機能に偏っています。
デジタルが「ノイズ」として切り捨てるものを、
積極的に「情報」として利用します。
変化し続けるアナログ的な「揺らぎ」を感知し、
処理する機能に偏っています。
デジタルが「ノイズ」として切り捨てるものを、
積極的に「情報」として利用します。
• アナログ的な揺らぎの中でのみ働く機能。
• ノイズや誤差を切り捨てずに情報の一部として扱うこと。
• 流れ、勾配、位相の変化といった、
境界や分類ではない要素を重視する「位相的直観」。
境界や分類ではない要素を重視する「位相的直観」。
この「I」は、「アナログ数学」の公理における
「揺らぎの包含」に対応しており、
誤差やノイズを情報として利用する知的能力を表します。
「揺らぎの包含」に対応しており、
誤差やノイズを情報として利用する知的能力を表します。
3. 想像 (Imagination) に偏っている現象
「想像(Imagination)」は、
連続的な空間や情報を認知的に拡張する機能に偏っています。
連続的な空間や情報を認知的に拡張する機能に偏っています。
• 連続空間を補間・外挿する力。
この「I」は、観測された離散的なデータ
(デジタルが強制的に作る境界)ではなく、
連続的な世界を前提とした上で、
知覚できない領域や将来の振る舞いを
推測・投影する能力に特化しています。
(デジタルが強制的に作る境界)ではなく、
連続的な世界を前提とした上で、
知覚できない領域や将来の振る舞いを
推測・投影する能力に特化しています。
まとめ:「3i/ATLAS」の構造
三つの「I」が重なり合うことは、
連続的な情報(Information)を、
揺らぎの中で働く直観(Intuition)を通じて受け止め、
その連続的な性質を拡張する想像力(Imagination)によって処理する、
という統合された
アナログ的分析のプロセスを意味します。
連続的な情報(Information)を、
揺らぎの中で働く直観(Intuition)を通じて受け止め、
その連続的な性質を拡張する想像力(Imagination)によって処理する、
という統合された
アナログ的分析のプロセスを意味します。
そして、このアナログ分析の結果として生まれる、
連続的な知の秩序を描く器が「ATLAS」であると定義されています。
連続的な知の秩序を描く器が「ATLAS」であると定義されています。
では、また。