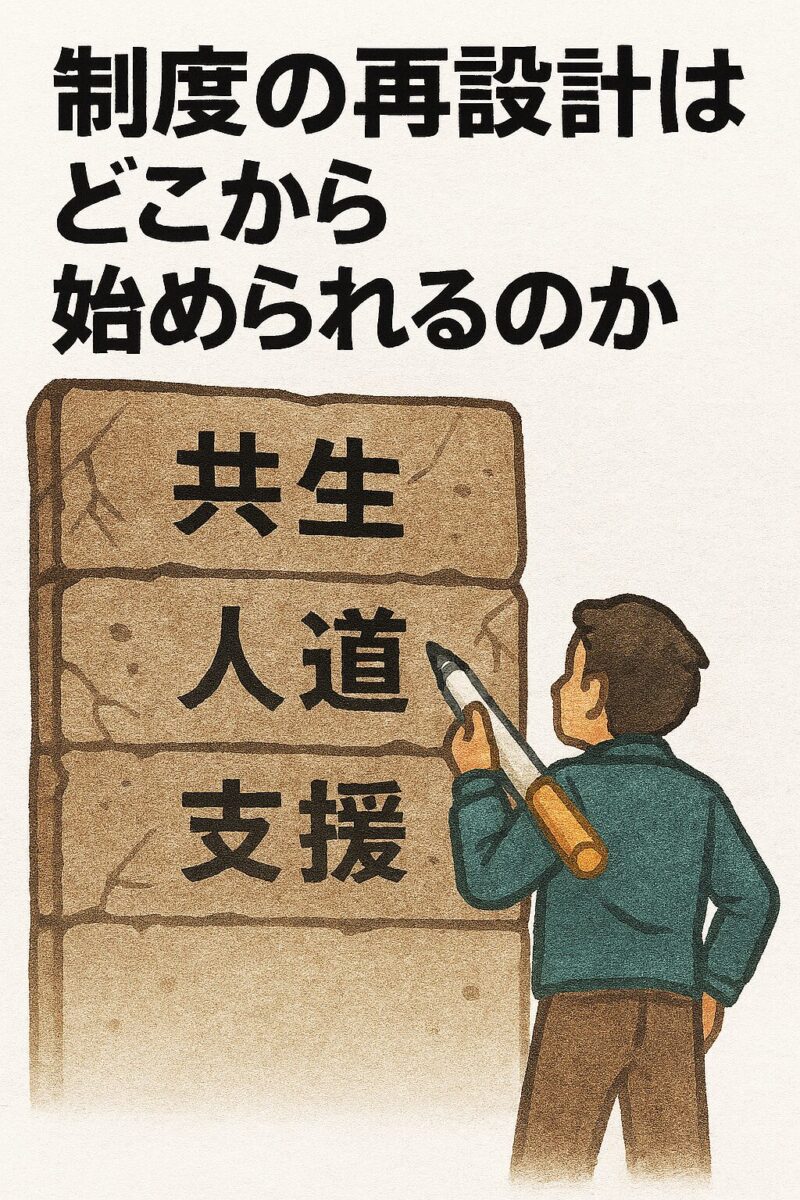こんにちは、\イッカクです/
第5回です。
制度の再設計はどこから始められるのか
──語りの再定義と市民的介入の技法
制度という言葉を聞いて、
あなたは何を思い浮かべるでしょうか。
法律?行政?仕組み?それとも、
どこか遠くの誰かが決めたルール?
私たちの日常に深く関わっているはずの制度が、
なぜか「自分のものではない」と
感じられてしまう。
その違和感の正体は、
制度が「語りの構造」として設計されていることにあります。
制度とは、単なる仕組みではなく、
「誰が語るか」「何を語るか」「誰を沈黙させるか」
という言語的支配の体系です。
制度の設計は、
しばしば行政や専門家によって独占され、
市民の言葉が入り込む余地は限られている。
だからこそ、制度の再設計は
「語りの再定義」から始めなければならないのです。
Ⅰ|制度の語りを問い直す技法
制度の語りは、抽象語によって構成されています。
「共生」
「人道」
「支援」
──これらの言葉は理念を示すようでいて、
実際には責任の所在や具体的な文脈を
曖昧にする装置でもあるのです。
たとえば「共生社会」と言われたとき、
誰と誰が共生するのか、
どのような条件で、
どのような摩擦があるのか
──そうした問いは語られません。
制度の語りは、
正当性の演出装置であると同時に、異議申し立ての遮断装置でもある。
だからこそ、
私たちは問い直さなければならないのです。
- 誰が語っているのか
- 何を語っていないのか
- 誰の声が排除されているのか
この問いを通じて、制度の言語支配に亀裂を入れることができます。
制度の語りを解体する技法は、
市民的介入の第一歩なのです。
Ⅱ|制度の語りに市民の言葉を挿入する
制度の再設計は、
上からの改革ではなく、
下からの語りの再構築によって可能になります。
SNSやブログ、
地域メディアなどを通じて、
市民が制度の語りに自らの言葉を挿入することで、
制度の正当性を再定義することができるのです。
ここで思い出したいのが、
元タレントであり教育者・外交官でもある
ゾマホン氏の事例です。彼は「郷に入っては郷に従え」と語り、
日本の文化や制度への適応を強く主張しました。
これは単なる
道徳的忠告ではなく、
制度の基本線
──文化的共通基盤と教育の重視
──を理解し、
それを自らの語りと実践で昇華させた例です。
ゾマホン氏は、日本のODAを称賛しつつも、
「支援とは自立を促すものであるべき」と語りました。
これは制度の語りを
「上からの恩恵」から
「対等な協働」へと再定義する試みであり、
制度の外部から来た者が、
制度の本質を理解し、
倫理的実践によって制度を
内側から変えようとする姿勢を示しています。
制度の奉仕を享受する立場でありながら、
その本質を忘れず、
制度を昇華させる語り手の存在
──それこそが、制度の再設計における
市民的可能性を象徴しているのです。
このような語りは、
制度の外部からの批判ではなく、
内部からの倫理的再定義として機能します。
つまり、制度の語りに
市民が参加することは、
制度そのものを変える力を持つのです。
そして重要なのは、
語りの挿入が一過性の声ではなく、
継続的な対話として制度に根付くこと。
制度は語られ続けることで、初めて公共性を帯びていくのです。
Ⅲ|制度を育てるという視点
制度は批判されるべき対象であると同時に、
育てるべき公共財でもあります。
制度の語りに
市民の言葉を挿入することは、
制度の正当性を再定義するだけでなく、
制度そのものを育てる行為でもあるのです。
制度を育てるとは、
制度の語りを倫理的に再構築し、
制度の運用に市民的責任を伴わせること。
制度の再設計とは、
語りの再定義であり、
その語りを担う市民的主体の構築でもあります。
制度は、語りによって設計され、
語りによって再設計される。
その語りに市民が介入し、
倫理的に再定義することで、
制度は単なる支配装置ではなく、
共に育てるべき公共の器となるのです。
そしてこの「育てる」という視点は、
制度を単なる批判対象としてではなく、
未来の公共性を担う器として捉えるための転換点でもあります。
制度を語るとは、制度を生きること。
制度を育てるとは、
制度に責任を持つこと。
そうした市民的実践が、
制度の再設計を可能にするのです。
制度の言語を握る者が制度の方向性を決めるならば、
私たち市民が語ることをやめた瞬間、
制度は私たちの手を離れていきます。
だからこそ、
語り続けること、
問い続けること、
そして育てることが、
制度の未来を左右するのです。
制度は、誰かが作ったものではなく、
私たちが語り、問い、育てるもの。
その営みこそが、制度の再設計の出発点なのです。