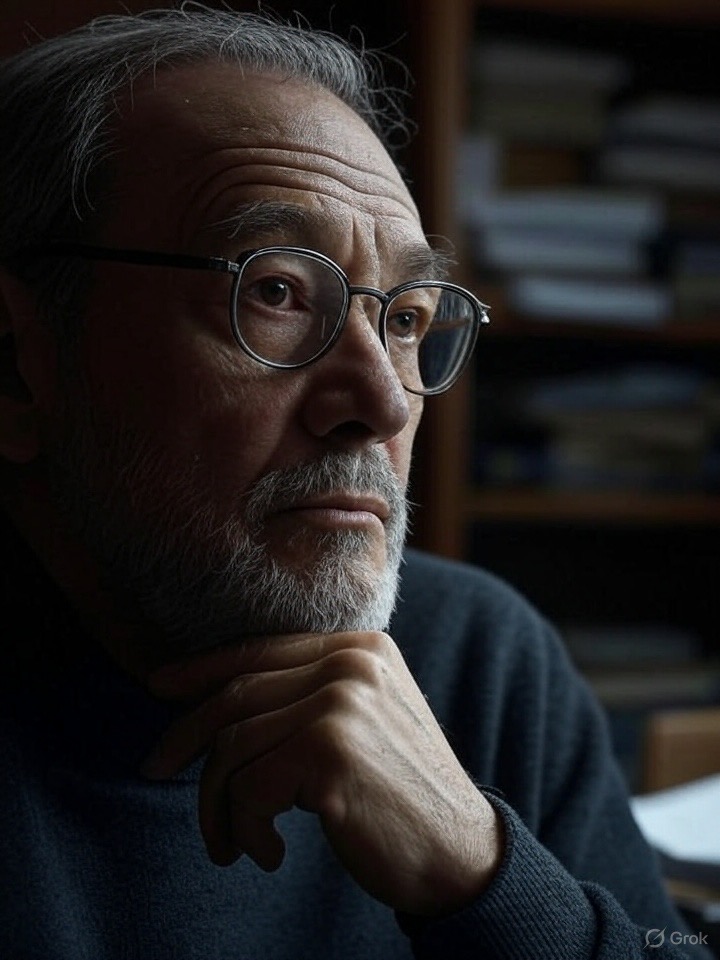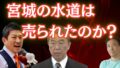こんにちは、\イッカクです/
今回は、論考:
「制度設計された大衆未来と生存選択」からの脱出の10回目です。
第10章 制度設計からの脱出
──“管理”と“進化”の岐路で
■変異する制度──“進化”の名のもとに
AI、バイオテクノロジー、ナノマシンといった先端科学技術の進展は、
人類の暮らしに利便性と加速的変化をもたらしている。
しかしその裏で進行しているのは、
「制度」そのものの性質の変異である。 従来、制度とは社会秩序を維持し、
共生を促すための道具であった。
だが今や、その制度が、
個々人の選択や行動、果ては思想傾向にまで干渉し得る
“枠組み”に変わりつつある。
たとえば、デジタルIDによって結びつけられた
健康記録・購買履歴・SNSの発言履歴は、
制度の内側から個人をスコア化し、
“善良な市民”としての条件を満たすか否かを判定する基準になり始めている。
この制度は、明確な暴力や弾圧を伴わず、
あたかも“透明”で“公平”に見える形で構築される──だからこそ、氣づきにくい。
■“共生”と“管理”のすり替え
制度が進化するにつれ、社会全体が“共生”を謳いながら、
実際には“管理”を強化しているという矛盾が浮上している。
「共に生きる」という言葉が語られる時、
それはかつて、互いに違いを認め、
尊重しあう思想だったはずだ。
だが、現在の制度設計における“共生”とは、
“管理可能な多様性”を許容するという、
条件付きの受容にすぎない。
そして“管理可能な多様性”とは、
数値化でき、監視でき、
アルゴリズムで分類できるという性質を有していなければならない。
こうして、
制度の内部で許される“自由”は、
あらかじめ設定された範囲内の“選択肢”に制限されることになる。
選べる自由はあるが、
創り出す自由は排除される構造。
このように、制度が進化すればするほど、
「誰のための制度か」という本質的問いが、意図的に隠蔽されてゆく。
■脱出のヒントは「制度以前」にある
このような制度設計から抜け出すには、
「制度以前」に遡る必要がある。
それは、人類が制度を生み出す前の、
もっと根源的な“共鳴”に立ち戻ることを意味する。
縄文期の暮らしを引き合いに出すまでもなく、
人々はかつて、“氣”の流れや“場”の空氣を察して動いていた。
共鳴により判断し、
異質なものを無理に統合せず、
それぞれの“間”を保つことで全体が調和していたのである。
その時代に制度がなかったわけではない。
ただ、それは記号化された法体系というよりも、
自然と呼応した“生きた了解”だった。
現在のように、
中央のサーバーが人間の行動を記録・分類し、
再生産する制度とは、根本的に異質なものである。
■制度の“外側”で、未来を紡ぐ
現代社会において、制度の“外側”で生きることは、
いわば“不便”で“非効率”な選択かもしれない。
しかし、それこそが新しい未来を紡ぐ糸口になる。
制度に依存せずに物や労力を交換し合うローカル・エコノミー、
貨幣を介さない贈与や共助の仕組み、
小さな場に根ざした暮らしの知恵。
これらはすべて、
“脱制度”の胎動である。
それらは、抗うためにではなく、
“本来の人間性”を取り戻すために生まれてくる。
そして、制度が人間を管理するのではなく、
人間の“共鳴”が制度の形を決めていく
──そんな逆転が起きる兆しでもある。
■おわりに──“見えない意志”と向き合う
制度は、見えない意志によって設計される。
それは時に国家であり、
時に資本であり、
あるいは技術そのものかもしれない。
そして私たちは、気づかぬうちに
その意志に沿って“生かされて”いる。
だが、人間には“氣づく力”がある。
氣づいた時、
制度の外側に選択肢が現れる。
それは“逃げ道”ではない。
特に日本病の日本人は
“生き治す道”である。
だからこそ、制度の変容をただ嘆くのではなく、
その背後にある構造と意志を見極める目を持とう。
そして、一人ひとりの“共鳴”が重なった先に、
“制度”という名の檻を越える未来が、静かに立ち上がるのだ。
完。
では、また。