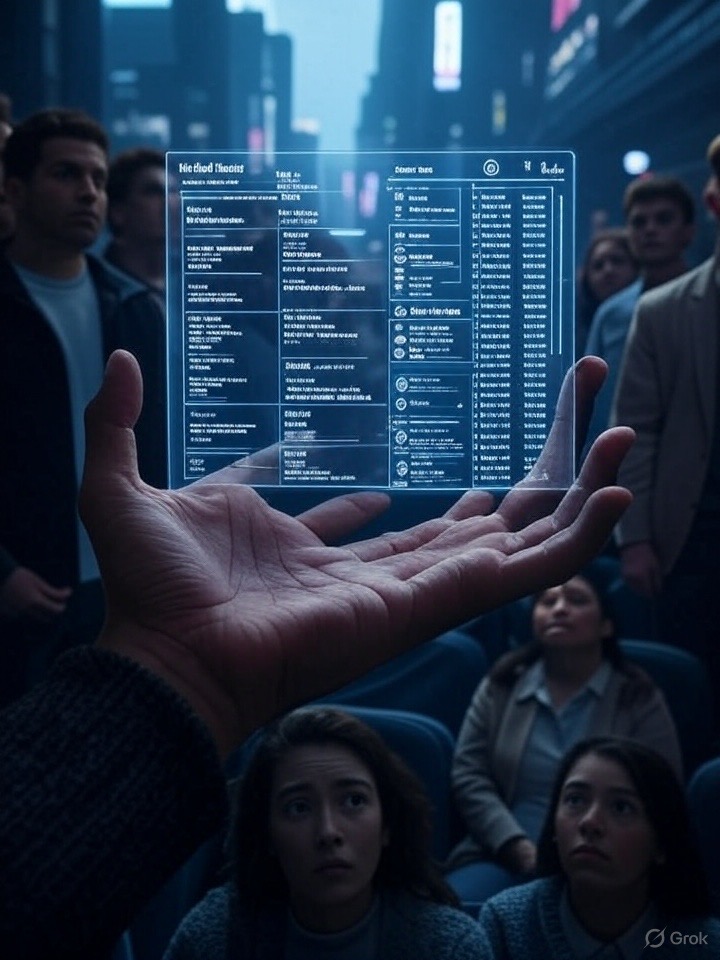こんにちは、\イッカクです/
今回は「論考:科学という劇場」の4回目です。
第4章 通貨のリセット──信用と自由が紐づけられる社会へ
2020年以降のパンデミックを経て、世界は大きく変貌した。
その中で見落とされがちなのが、
通貨制度の静かなリセットである。
感染症対策という“緊急事態”がもたらしたのは、
人と人との分断や監視の常態化だけではない。
もうひとつ、社会の根幹を成す「お金」の仕組みにも、
大きな転換が仕込まれていた。
その名は──CBDC(中央銀行デジタル通貨)。
これは、各国の中央銀行が
直接発行・管理する新しい通貨であり、
物理的な紙幣や硬貨とは異なり、
すべてがデジタル上で記録・管理される。
いわば、完全にトレーサブル(追跡可能)なマネーである。
いまや、世界の多くの国がこのCBDC導入を準備・実験している。
日本銀行も「デジタル円」の実証実験を進めており、
一部自治体では“地域通貨”や“ポイント連携”という名で、
すでにCBDCの前段が始まっている。
だが、この新通貨の本質は、単なる利便性や効率性ではない。
その根底には、
通貨が「管理と信用の手段」として機能する社会の構築がある。
たとえば──
どこで何を買ったか
どれだけエネルギーを消費したか
健康診断は受けているか
接種履歴やSNSでの発言内容はどうか
これらの情報が、デジタルIDと連動した個人信用スコアに結びつくとき、
通貨は「中立な交換手段」ではなく、ご褒美と罰則の装置になる。
つまり、「お金の使用条件」が、
行動の自由を規定する時代が来るのだ。
「あなたは接種していないから、この支払いは制限されます」
「あなたの炭素排出量が上限に達したため、飛行機チケットは購入できません」
「投稿内容が基準に反したため、ポイントは付与されません」──
そんな未来は、もはや“陰謀論”ではなく、
公式の政策文書にさえ記されている。
それは「プログラマブルマネー(条件付き通貨)」と呼ばれ、
“誰に、いつ、どのような用途で使わせるか”
をプログラムで制御できる通貨である。
これは金融の話ではない。
人間の自由に関わる、本質的な問題である。
かつて「お金」は、手にすれば誰でも使える“中立な手段”だった。
だがこれからは、
使うために“従順”であることを求められる時代が始まる。
つまり、通貨が統治のインフラとなるのだ。
パンデミックによって可視化された「科学という劇場」は、
このCBDC導入という第2幕に連結している。
“感染対策”という名目でデジタル管理が進み、
次は“経済効率と公平性”の名のもとに、行動の選別が始まる。
この流れに「違和感」を抱いた者も少なくないはずだ。
だが、その違和感を「氣づき」へと昇華させるには、
単に制度を批判するのではなく、
自分の生き方そのものを見直す視点が必要になる。
「お金とは何か?」
「信用とは誰が与えるものか?」
「自由とは、条件付きで与えられるものなのか?」
これらの問いを抱き直すとき、
劇場の観客席を離れ、自ら舞台に立つ者としての覚悟が求められてくる。
では、また。