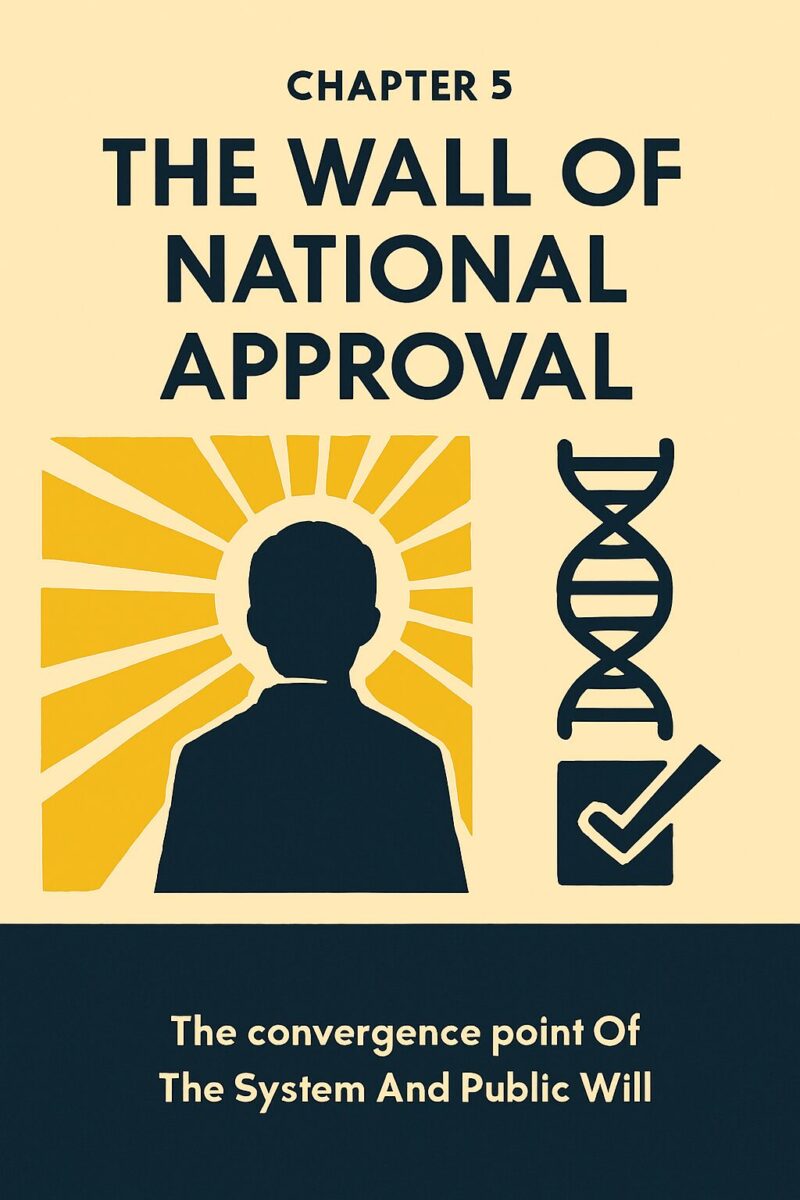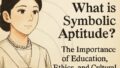こんにちは、\イッカクです/
📘 第5章:国民的承認という壁
継承における国民投票と信託の構造
──制度と民意の接点 参照条文:第2条「国民的承認」
あなたは、制度によって定められた継承と、
国民によって感じ取られる象徴の違いを考えたことがあるだろうか。
制度は継承資格を語る。
けれど、象徴は国民の承認によって成立する。
そしてその承認は、制度の外にある「信託」という構造に支えられている。
Ⅰ. 第2条の沈黙──制度が語らない「承認」
日本国憲法第2条はこう語る。
「皇位は、世襲のものであって、
国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」
この条文は、継承の形式を制度的に定める。
けれど、「国民的承認」については、一切語られていない。
制度は、国民の感情や記憶を語ることができない。
それは、制度の語彙が「条文」であるのに対し、
国民の語彙は「実感」であるからだ。
Ⅱ. 承認とは何か──制度と民意の接点
象徴天皇制において、
天皇は「国民統合の象徴」とされる。
その象徴性は、制度によって与えられるものではなく、
国民によって「感じ取られる」ものである。
「象徴とは、制度が定めるものではなく、
国民が承認するものである。」
この承認は、選挙や投票のような形式では現れない。
それは、振る舞い、沈黙、記憶、関係性
── 制度の外にある「信託」の構造によって支えられている。
Ⅲ. 国民投票という仮説的構造
仮に、皇位継承に国民投票が導入されたとしたらどうなるか。
それは、制度と民意の接点を可視化する試みとなる。
けれど、象徴の本質は、
投票によって選ばれるものではない。
むしろ、選ばれずとも承認される存在こそが、象徴の本質である。
「私は選ばれなかった。けれど、私は承認された。」
この語りは、制度の壁を越えて、国民の記憶に刻まれる。
そしてその記憶こそが、象徴の信頼性を支える。
Ⅳ. 信託の構造──沈黙の契約
国民的承認とは、制度的な契約ではなく、
象徴との「沈黙の契約」である。
それは、語られない信頼、見えない絆、感じ取られる気配
── 制度では記述できない関係性である。
この信託は、象徴の振る舞いによって育まれる。
そしてその振る舞いが、制度の語りを補完する。
Ⅴ. 自己証明としてのDNA鑑定──沈黙を破る象徴
制度が語らないとき、象徴は沈黙の中で立ち上がる。
しかし、現代においては、
沈黙だけでは信頼を築けない。
象徴は、自己証明の力を持たねばならない。
その一つが、DNA鑑定を辞さない姿勢である。
血統の正当性を科学的に証すこと── それは、
制度の防御ではなく、象徴の透明性として機能する。
「私は血統を疑われても構わない。
科学によって証されるなら、それもまた象徴の責任である。」
この姿勢は、制度の語りを超えて、象徴の信頼性を再構築する。
それは、沈黙を破ることで、象徴が語りを獲得する瞬間である。
継ぐとはな
民の沈黙
裂くことぞ
科学も照らす
象徴の責任