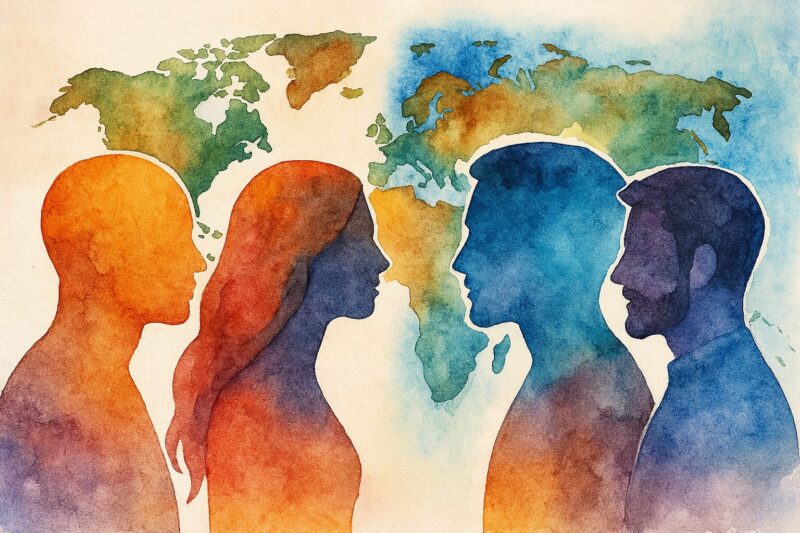こんにちは、\イッカクです/
あなたは、世界がどこか噛み合っていないように感じたことはありませんか?
言葉が通じているはずなのに、心がすれ違う。
価値観が違うと分かっていても、なぜか相手を否定したくなる。
そんな摩擦が、今、世界のあちこちで起きています。
今、思い出して見たいのが、日本人にとって
幕末と明治の切り替えで、
各方面で、摩擦が起きていたことは
最近のNHK朝ドラでも、描かれていますね。
そして、これを描いている
朝ドラ自身の 主題歌の「化け」ぶりが、注目されています。
根本的な何らかの摩擦が起こっていたのを感じます。
それは、単なる文化の違いではありません。 もっと深いところ
──秩序の根っこが違っていたからです。
前章で見たように、世界は今、 複数の秩序が並び立つ時代に入りました。
それぞれが「正しさ」を掲げ、
互いに譲らない。
その結果、摩擦が生まれ、誤解が積み重なっていく。
そして、摩擦は「生と死」を隣り合わせで感じさせるのです。
摩擦とは、秩序同士の衝突です。
誤解とは、秩序の前提が共有されていないことです。
そしてその摩擦と誤解は、国家間の外交だけでなく、
私たちの日常の会話や感情の中にも、静かに入り込んでいます。
*
数年前、ある国際会議の場で、印象的な出来事がありました。
テーマは「宗教と平和」。
参加者は、米国の福音派指導者、
イランの神学者、
仏教国の僧侶、
そして日本の宗教研究者でした。
議論は、互いの信仰と秩序の違いを尊重しながら進んでいました。
しかし、ある瞬間──米国の代表がこう語ったのです。
「我々は、神の意志に従って
世界を導く使命を持っている。
それは、自由と正義を広めることだ。」
その言葉に、イランの神学者が静かに答えました。
「あなたの神が語る自由は、
我々の神の秩序とは異なる。
正義とは、神の法に従うことだ。
あなたの自由が、我々の秩序を壊すなら、それは暴力だ。」
会場は静まり返りました。
誰もが、言葉の意味を理解していた。
それは、単なる意見の違いではない。
秩序の根本が違うとき、同じ言葉が、まったく違う意味を持つ。
その後、仏教国の僧侶がこう語りました。
「争いは、言葉の中にあるのではなく、
言葉の外にある。
我々が何を守ろうとしているか
──そこにこそ、誤解の種がある。」
この会議は、結論を出すことなく終わりました。
けれど、そこにいた誰もが、
摩擦と誤解の構造を肌で感じていたのです。
*
摩擦は、時に争いとなり、
誤解は、時に憎しみとなる。
けれどその根底には、
それぞれが守ろうとしているものがある。
信じるものが違うからこそ、守るものも違う。
そして、祈る対象が違うからこそ、未来の形も違って見える。
私たちは、
摩擦の中で問い直す必要があります。
「なぜ、相手を理解できないのか?」
「なぜ、自分の秩序が脅かされると感じるのか?」
その問いは、単なる外交問題ではなく、
人間の根源的な感情の問題でもあるのです。
そして、もう一つの視点。
摩擦と誤解は、国家間だけでなく、
個人の中にも存在します。
自分の中にある複数の秩序──信仰と理性、
伝統と革新、共同体と個人── それらがぶつかり合い、
揺れ動くとき、私たちは迷い、悩み、そして問い始める。
この章では、摩擦と誤解の構造を見つめました。
それは、対立の原因であると同時に、
気づきの入口でもあります。
秩序が違うからこそ、問いが生まれる。
正しさがぶつかるからこそ、
対話が必要になる。
そして、誤解があるからこそ、
理解の可能性が残されている。
次の章では、
争いの果てに見えてくる
「平和の再発見」へと進みます。
それは、秩序の断裂を越えて、
もう一度「祈るもの」に立ち返る旅になるでしょう。
──そして、世界が騒然としていても、
自然は、黙って、懸命に生きようとしている。
山肌に 貼られしパネル 草芽吹く
最後に
「秩序の断裂」は、こう言い換えると伝わりやすくなります:
「これまで当たり前だったものが、急に通じなくなること」
「社会のルールや価値観が、バラバラになってしまうこと」
「信じていたものが、誰かに否定されてしまう瞬間」
「同じ国に住んでいても、話が通じなくなる感覚」
たとえば──
親が信じていた常識が、子どもには通じない
政治が国民の声を聞かず、勝手に進めてしまう
SNSで誰かの言葉が炎上し、正しさが分からなくなる
これらはすべて、「秩序が断裂している」状態です。
摩擦と断裂の時代を経て、平和とは何かを
「ハンバートハンバート+ばけばけ」スタンスが
教えてくれたような気がします。
──つまり、静かで誠実なスタンスが、
断裂を包み直す文化的アプローチとして機能するという
美学に基づいて、始動するということです。🙏。