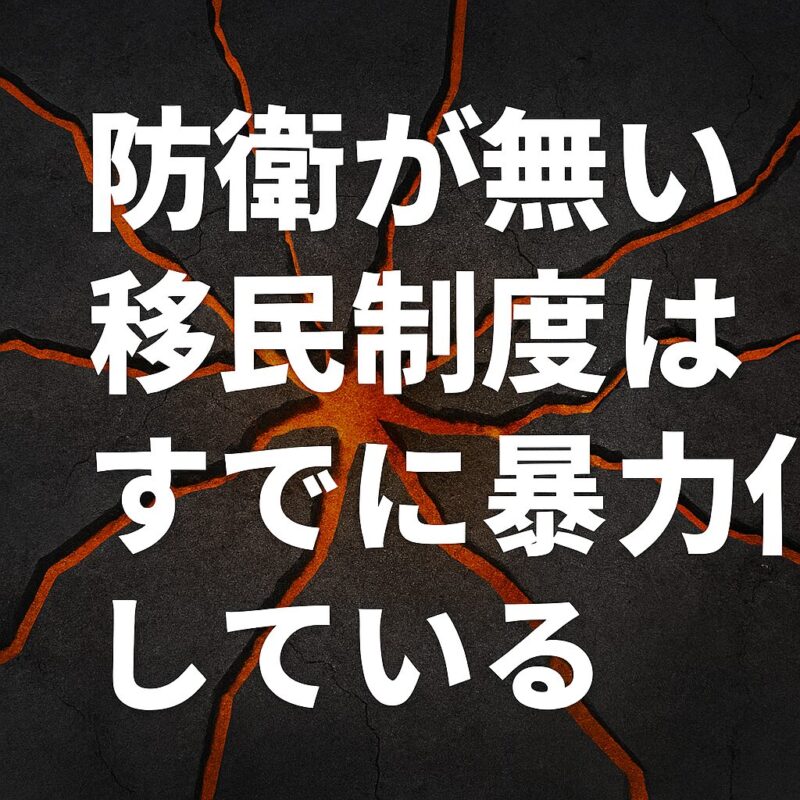防衛が無い移民制度は
すでに暴力化している
新宿区・新大久保。
多文化共生の象徴とされるこの街で、近年、
路上で礼拝をするイスラム教徒の姿が目立つようになった。
彼らにとって礼拝は宗教的義務であり、
信仰の表現である。
https://youtu.be/54mwl7wZVfE
しかし、公共空間での宗教的振る舞いが
地域住民の生活規範と衝突するとき、
それは単なる文化的違和感ではなく、
制度の不在が生む構造的暴力となる。
この現象は、単なる一地域の問題ではない。
ヨーロッパの各都市では、すでに「制度なき移民受け入れ」
が社会の秩序を揺るがす事態に発展している。
宗教的自由と公共秩序の均衡が崩れたとき、
国家は制度的防衛を果たせず、
結果として市民社会が分断される。
ヨーロッパが直面する「制度の空白」
フランス・ベルギー・スウェーデンなどでは、
イスラム教徒の人口が急増し、
都市郊外には事実上シャリーア法が適用される
コミュニティが形成されている。
フランスでは、若年層イスラム教徒の57%が
「シャリーア法は国家憲法よりも上位にある」
と考えているという調査結果もある。
ベルギーのブリュッセルにあるモレンベーク地区では、
若者の失業率が40%を超え、
犯罪率も高い。
この地域は過去に複数のテロリストを輩出しており、
刑務所内での過激化も深刻な問題となっている。
スウェーデンでは、
移民系住民が集中する地域で暴動や放火事件が頻発し、
警察の介入すら困難な「ノーゴーゾーン」が報告されている。
ドイツでは、移民政策の急拡大により、
学校や病院などの公共サービスが逼迫し、
地域住民との摩擦が顕在化している。
宗教的慣習に基づく要求が行政に突きつけられ、
教育現場では男女分離や宗教的祝祭日の扱いを巡って議論が絶えない。
ヨーロッパの世俗国家は、
イスラムという越境的宗教に対して、
自らのアイデンティティを「神話化」することで応じている。
フランスでは、テロ事件後に
国旗を掲げ、マルセイエーズを歌い、
犠牲者を記憶する儀式が急増した。
これは、国家が宗教的役割を再び担い始めたことを意味する。
制度が宗教に対して無防備であるとき、
国家は象徴によって秩序を再構築しようとする。
日本における制度的盲点
日本でも、移民政策の拡大に伴い、
宗教的配慮が制度設計の中で問われ始めている。
仙台イスラム文化センターの代表は、
「日本の習慣を学び、できる限り調和を図るよう努めるべき」と語っている。
これは、宗教的自由と地域文化の共存を模索する姿勢であり、
制度的調整の必要性を示唆している。
しかし、東京都新宿区のように、
礼拝スペースが不足している地域では、
路上礼拝という形で宗教的義務が公共空間に現れる。
これは、
制度が整備されていないことによる「空白の暴力」であり、
地域住民との摩擦を生む。
公共空間は誰もが利用する場であるが、
宗教的行為が可視化されることで、
空間の意味が変容し、文化的緊張が生まれる。
さらに、衣食住・衛生・教育・宗教習慣など、
生活のあらゆる側面において、
制度的配慮がなければ、
摩擦は避けられない。
ハラル対応の食事、男女分離の衛生設備、
宗教的祝祭日の扱いなど、
行政が制度として整備していない限り、
共生は理念にとどまり、現実には衝突が起こる。
まるで、背後からこのことを知ってて
移民を敢行せよという指示がなされているようにも思えるのである。
(背後に、グローバリズム有り😱)
宮城県では、イスラム教徒の土葬ニーズに対応するための
墓地整備が検討されたが、
県民や市町村長の強い反発を受けて撤回された。
村井知事は
「やる意志はなかった」と語ったが、
発言の中には「批判があっても、これはやらなければならないと思っています」と
いった強い推進意志が垣間見えた。
制度設計の段階で市民的合意形成が欠如していたことが、
摩擦(=計画の頓挫)の根本原因である。
これは、基本的なことではあるが、権力者は
よく履き違いをして、計画を命令的にゴリ押しする。
そこには、必ず、大衆とのズレである「摩擦」が生じる。
つまり、摩擦を生じる=計画は頓挫する
という、方程式が太古から成り立っていたのである。
そこで、誤魔化そうとするから、なおさらに、
信頼は低下し、為政者は失職するのである。(次の選挙が楽しみ😱)
防衛なき制度は暴力化する。している。
制度とは元来、文化・秩序・倫理を守る盾である。
その盾が欠けたまま移民を受け入れることは、
共生ではなく制度的放置であり、社会的摩擦の温床となる。
宗教的自由は尊重されるべきだ。
しかし、それが公共空間の秩序を揺るがすとき、
国家は制度的防衛を果たさなければならない。
礼拝、服装、食事、衛生、教育──すべての生活文化において、
制度的配慮がなければ、
共生は幻想となり、
暴力的摩擦が現実となる。
ヨーロッパが今、制度の空白によって揺らいでいるように、
日本もまた、制度設計の不在が暴力化する瞬間に
立ち会っているのかもしれない。
行政が「多文化共生」を掲げるならば、
まず制度の防衛機能を整備すべきである。
市民の不安に応える説明責任、
公共空間の秩序を守る規範、
宗教的自由と地域文化の均衡
──これらを制度として設計しなければ、
共生は空疎なスローガンに終わる。
制度が防衛を欠いたとき、
文化的摩擦は暴力へと転化する。
それは物理的な衝突だけでなく、
空間の占有、価値観の押し付け、公共秩序の変容といった、
見えにくい暴力として社会に浸透する。
市民が違和感を覚えたとき、
それは偏見ではなく、制度の不在に対する直感的な警鐘である。
結語:制度設計こそが共生の前提である
「多文化共生」という言葉が空疎な理想に終わらないためには、
制度の防衛機能が不可欠だ。
文化的摩擦を予防し、
公共空間の秩序を守り、
市民の不安に応える制度設計こそが、真の共生を可能にする。
防衛なき移民制度は、すでに暴力化している。
私たちはその現実を直視し、制度の言語で語り直す必要がある。
制度設計は、
文化の境界を守る最後の砦であり、共生の前提条件である。
制度設計こそが共生の前提である
制度の暴力化とは、
単に物理的な衝突を意味するのではない。
公共空間の意味が変容し、市民の生活規範が侵食されるとき、
制度はその防衛機能を失い、
見えない暴力として社会に浸透する。
宗教的自由が制度的に保障されるべきであることは疑いない。
しかし、それが公共秩序を揺るがすとき、
国家は制度の盾を構築しなければならない。
では、私たち市民はどうすればよいのか。
制度の空白に対して、
沈黙することなく、言語で応答すること。
違和感を感情として流すのではなく、
制度的問いとして言語化すること。
行政の説明責任を求め、
公共空間の秩序を守るための制度設計に市民の視点を注入すること。
これらはすべて、
私たちが制度に介入する技法である。
制度の言語を奪い返し、
文化的摩擦を予防するための構造を
市民の手で築くこと。
それが、暴力化する制度に抗する唯一の方法である。
共生とは、
制度的防衛が整った上での対話であり、
無防備な受け入れではない。
防衛なき移民制度は、すでに暴力化している。
だからこそ、私たちは
制度の言語を鍛え、
市民的監視の技法を磨き、
公共空間の秩序を守る責任を
引き受けなければならない。
制度設計は、国家の仕事であると同時に、市民の責務でもある。
以上