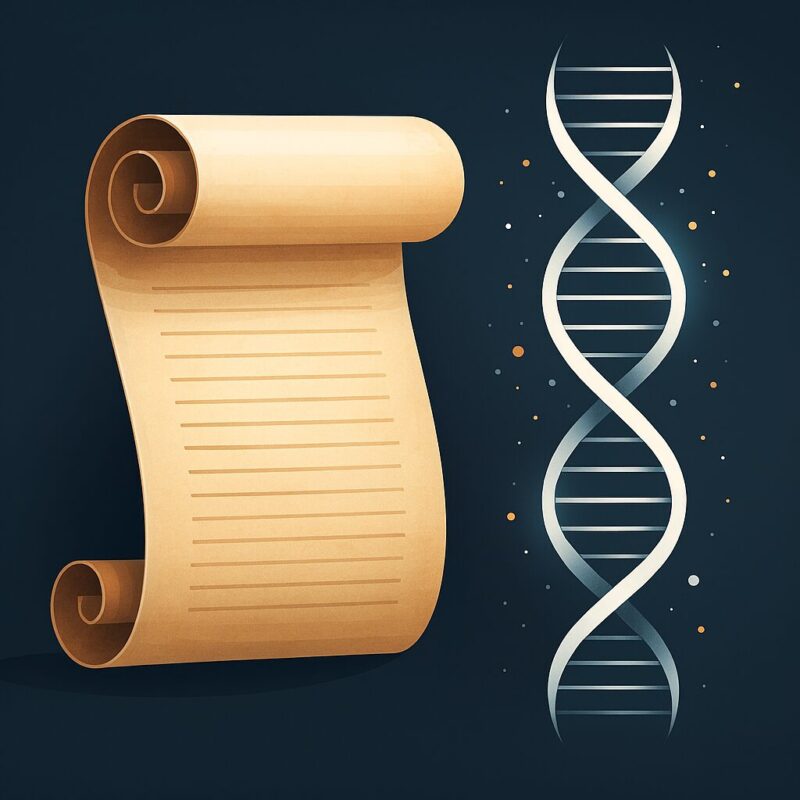こんにちは、\イッカクです/
今回も「象徴再構成論──男系男子を超えて」論考シリーズの7回目を
以下、置きます。
第7章 血統の検証と沈黙の裂け目
―血統の透明性と制度の沈黙が交錯する場面―
ねえ、あなたは「血統」って聞いて、
何を思い浮かべますか? 家系図?戸籍?
それとも、DNAの螺旋構造?
私たちはふだん、血統という言葉をどこか遠いものとして扱っているけれど、
実はそれは、制度の奥深くに静かに息づいている、とても現実的な構造なんです。
とりわけ、日本において最も象徴的な血統といえば、
やはり天皇家でしょう。
「万世一系」という言葉が、
まるで神話のように語られてきました。
でも、その“万世”の系譜が、
制度によってどこまで検証されているのか
―― そう問うと、急に空気が変わるのを感じませんか?
実は、現行の制度では、
天皇の血筋が本当にDNA的につながっているかどうかを
制度的に検証する仕組みは存在しません。
戸籍は非公開、DNA鑑定も行われない。
つまり、制度は「血統を守る」と言いながら、
その証明を放棄しているんです。
たとえば、万が一の話ですが、
もし血筋でない人物が、
何らかの事情で皇族に組み込まれていたとしたら?
制度はそれを明らかにするどころか、
むしろ覆い隠す方向に働くでしょう。
なぜなら、制度は“神話”を守るために設計されているからです。
そしてその神話は、検証されないまま、
象徴として国民に差し出される。
制度は“神話”を守るために・・・そうですね
原発事故の”安全神話”は、現実的に
崩壊してしまいました。
この構造、あなたはどう感じますか?
天皇の系譜には、
実は女性天皇も存在していました。
歴史上、8人10代の女性天皇が即位しています。
たとえば、推古天皇(第33代)は日本初の女性天皇であり、
持統天皇(第41代)は天武天皇の皇后として、
後に孫の文武天皇へと皇位を継がせました。
他にも元明天皇、元正天皇、孝謙天皇、称徳天皇、明正天皇、後桜町天皇などがいます。
つまり、女性が天皇になること自体は、
歴史的に否定されていないんです。
にもかかわらず、
現在の皇室典範では「男系男子」に限定されている。
この矛盾もまた、
制度が“血統”をどう扱っているかを物語っています。
制度は、血統を語る。
けれども、語らないことを選ぶ場面では、
沈黙という技術を使う。
そしてその沈黙の中で、
国民との間に“疑惑という空白”が生まれる。
私たち庶民は、戸籍を提出し、DNA検査を受け、
時に「血筋」を証明しなければならない場面に直面します。
でも、象徴たる存在には、それが求められない。
むしろ、検証されないことが
“神聖性”として制度に組み込まれている。
この非対称性―― あなたは、どう受け止めますか?
私は思うんです。
血統の検証が制度的に行われないということは、
制度が象徴に依存しているということ。
そしてその象徴が揺らいだとき、制度は語れなくなる。
庶民の切実な祈りは、制度帳簿に記載されない。
それは、税金でもなく、戸籍でもなく、
ただ「信じたい」という気持ちのカタチ。
でも、その祈りが空白に吸い込まれていくとき、
象徴性は静かに、確実に、揺らぎ始める。
血統とは、DNAでつながる実在の系譜。
制度は、その系譜を語る装置であると同時に、
語らないことを選ぶ装置でもある。
そして、沈黙の裂け目に灯火を差し込む者が現れるまで、
制度は語らない。
それでも、私たちは問わなければならない。
その血統は、誰のために守られているのか。
その沈黙は、誰の声を封じているのか。
そして、私たちの祈りは、どこに記されるべきなのか。
この章は、制度の奥に潜む“語られざる構造”を照らすものです。
次章「象徴の誓約」では、
継承儀式という“形式”が、
制度から象徴へとバトンを渡す場面を描いていきます。
そこでもまた、語られないものが、制度の中核に座っているのです。
つづく。