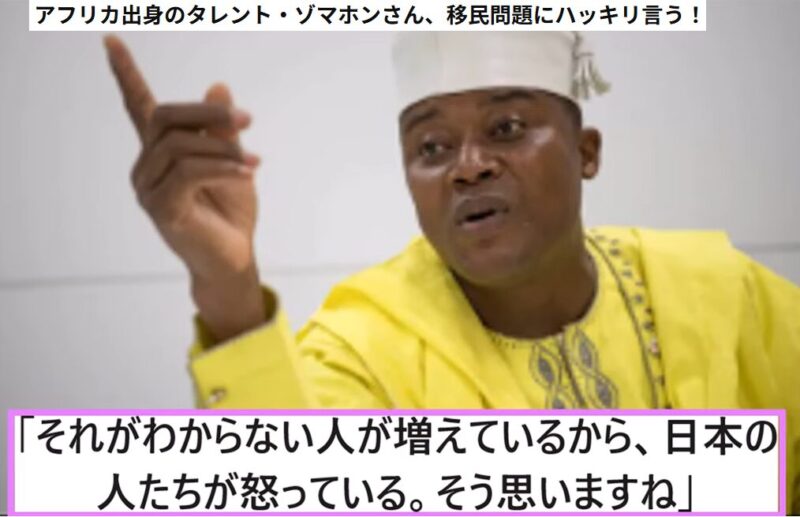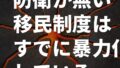こんにちは、\イッカクです/
今回は、【連続企画】市民が制度をつくるって、
どういうこと?について
こんにちは。
この連載では、
「制度とは何か」
「市民が制度をつくるとはどういうことか」
を問い続けてきました。
前回は、制度の語りに市民が介入することで、
制度の暴力に対する防衛線が築かれることを考察しました。
今回は、制度の語りが公共性を回復する瞬間
──つまり、市民と制度が協働する構造について掘り下げます。
制度は誰かが一方的に設計するものではなく、
市民の語りが挿入されることで
初めて公共財としての意味を帯びます。
制度と市民が交差するとき、
制度は支配装置から共創の器へと変容するのです。
制度と市民の関係性の再定義──「参加」ではなく「語り」
制度に市民が関与するというと、
「参加」や「意見提出」といった形式的な関与が想定されがちです。
しかし、本稿で扱う「協働構造」とは、
制度の語りに市民が自らの言葉を挿入し、
制度の設計思想そのものに介入することを意味します。
制度の語りが抽象語で覆われている限り、
市民の生活実感は制度に反映されません。
だからこそ、
市民は制度の語りに具体的な言葉を持ち込み、
制度の設計思想に倫理を注入する必要があります。
ゾマホン氏の「もの語り」──制度の外部者が公共性を回復した瞬間
ここで、制度の語りに介入した
市民的主体の象徴として、
ゾマホン・ルフィン氏の経験を取り上げます。
彼はベナン共和国出身の移民者でありながら、
日本社会に対して強い倫理的問いを投げかけた語り手です。
ゾマホンの語りは、
制度の外部から発せられた「もの語り」であり、
制度の設計思想に対する物語的介入でした。
彼は、日本社会の文化的偏見や制度的沈黙に対して、
情熱と構造認識を伴った語りで応答しました。
ゾマホンの語りは、
制度の暴力に対する市民的防衛であり、
制度の未来を担う語りの実践である。
彼の語りは、「制度の外部者」が「制度の語り手」へと
転換する可能性を示し、
制度の語りに公共性を回復させる実践として機能しました。
協働の条件──制度と市民が対話するために必要なもの
制度と市民が協働するためには、以下の条件が必要です:
制度側:透明性・説明責任・語りの開放性
市民側:構造的認識力・倫理的問いかけ・言語的介入力
両者の間にある「語りの空間」の設計と維持
制度が市民の語りを受け入れる構造を持たない限り、
協働は成立しません。
逆に、市民が制度の語りに介入する覚悟と技法を持たない限り、
制度は公共性を帯びることができません。
協働の実践──制度の語りに市民が介入した事例群
制度の語りに市民が介入した事例は、すでに各地で生まれています。
水道事業の外資支配構造に対する市民的問いかけ
教育制度・教科書検定への市民的介入
移民制度に対する地域住民の語りの再構築
SNS・議会傍聴・政策提言など、語りの実践としての市民的行動
これらの実践は、
制度の語りに亀裂を入れ、
公共性を回復する市民的攻撃であり、
制度の暴力に対する防衛の言語です。
制度の語りを共創するとは──公共性の再構築
制度は語りによって設計され、
語りによって育てられます。
市民が制度の語りに責任を持つことで、
制度は支配装置ではなく、公共財としての意味を帯びます。
協働とは、
制度の語りを市民が引き受けること。
制度の語りに市民の倫理が挿入されるとき、
制度は暴力ではなく器となり、社会を支える構造へと変容します。
結び──制度の言葉を誰が握るのか
制度の未来は、語りの共有にかかっています。
制度の言葉を誰が握るのか
──その問いを、私たち自身が引き受ける時代が始まっています。
制度は、
誰かが作ったものではなく、
私たちが語り、問い、育てるものです。
制度の語りに市民が介入することで、
制度は支配装置から公共財へと変わります。
次回は、
「制度の語りを可視化する技法
──図解・言語・メタファー」について
掘り下げていきます。
制度の語りを市民が手に取るための技法とは何か
──その問いを、次回で展開します。