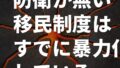【連続企画】市民が制度をつくるって、どういうこと?
第6回 制度の語りを昇華させる市民的主体の条件 ──制度の暴力から社会を守るために
こんにちは。この連載では、
「制度とは何か」
「市民が制度をつくるとはどういうことか」を、
問い続けてきました。
前回は、制度の再設計は語りの再定義から始まること、
そして市民が制度の語りに自らの言葉を挿入することで
制度を育てる可能性について考えました。
今回は、制度の語りに介入する
「市民的主体」とは何かを掘り下げます。
制度の語りが暴力的に機能する時代において、
私たちはその語りを昇華させる主体として、
どのような条件を備え、
どのような行動を取るべきなのか――それが本稿のテーマです。
制度の語りが暴力になるとき
制度は、語りによって設計され、
語りによって運用されます。
問題は、その語りが
「誰かの目的のために」使われるときです。
たとえば、移民制度が
「労働力確保」
「国際貢献」
「人道支援」といった抽象語で語られる一方で、
地域社会の摩擦や福祉制度の圧迫、
市民の不安は語られません。
制度の語りが抽象化され、
現実の摩擦を覆い隠すとき、
それは制度的暴力として機能します。
制度の語りが
「誰かの利益のために」
「誰かの沈黙を前提に」
設計されているならば、それは制度の暴力です。
そして今、
世界各地で制度の暴力が社会を揺るがしています。
ヨーロッパでは、
移民制度が国家の統治構造を崩し、
騒乱が広がっています。
制度が「支援の装い」で導入されながら、
実際には国家の分断と社会的衝突を生んでいるのです。
市民的主体とは何か?
制度の語りに介入する市民的主体とは、
単なる批判者ではありません。
制度の語りを倫理的に問い直し、
再定義し、公共性を回復する語り手です。
制度の暴力に対して、
冷静に構造を見抜き、倫理的な言葉で対抗する存在です。
その条件は、以下のように整理できます:
- 構造的認識力:制度の設計思想と語りの支配構造を見抜く力
- 倫理的問いかけ:誰が語り、誰が沈黙させられているかを問う姿勢
- 言語的介入力:制度の語りに市民の言葉を挿入する技法
- 公共的責任感:制度を育てる主体としての覚悟
これらを備えた市民的主体こそが、
制度の暴力から社会を守る防衛線となるのです。
制度の暴力に対する市民的行動──語りの実践としての「攻撃」
制度の暴力に対して、市民が取るべき行動は
「語りの実践」であり、具体的な介入です。
それは単なる批判ではなく、
制度の語りに
亀裂を入れ、
公共性を回復するための行動です。
たとえば、制度の不整合や加害構造に気づいた市民が、
以下のような行動を取ることは、
制度の語りに対する市民的「攻撃」として機能します:
- 抗議の電話・メール:
行政機関や議員事務所に対して、
制度の設計思想や語りの欺瞞性を指摘する。 - 街頭演説・チラシ配布:
制度の語りが市民の生活にどのような影響を与えているかを、
具体的な事例とともに可視化する。 - SNSでの構造的発信:
制度の語りの構造を図解・言語化し、拡散する。 - 市民連携による質問状・公開声明:
制度の語りに対して、
市民が連名で問いかける文書を作成し、公開する。 - 議会傍聴・政策提言の提出:
制度の設計現場に市民が足を運び、
語りの空間に直接介入する。
これらの行動は、
制度の語りに対する「市民的攻撃」であり、
制度の暴力に対する防衛の実践です。
制度の語りが抽象語で覆われているからこそ、
市民は具体的な言葉で語り直す必要があります。
制度の暴力は「見えない暴力」である
制度の暴力は、殴る・蹴るといった
物理的な暴力ではありません。
それは、
語りの独占、
説明責任の回避、
対象者の沈黙化といった、
構造的・言語的な暴力です。
だからこそ、対抗するには「語りの力」が必要です。
制度の語りが「善意の装い」で導入されながら、
実際には国家の統治構造や社会の倫理を破壊する
道具として使われている
――この構造に対して、市民ができる防衛は
「語りの再定義」であり、
「制度の目的化」に対する倫理的抵抗です。
たとえば、移民を前提とする渡航者の扱いについて
X上で見かける「帰るワケねーだろ!」という言葉は、
制度の語りに対する市民的カウンター語です。
それは、制度の構造を見抜いたうえでの倫理的抵抗であり、
制度の暴力に対する防衛の言語です。
制度を育てる語り手として
制度は、語りによって設計され、
語りによって再設計されます。
制度の語りに市民が介入し、
倫理的に再定義することで、
制度は単なる支配装置ではなく、
共に育てるべき公共の器となるのです。
制度の暴力から社会を守るには、
制度の語りを市民の手に取り戻すこと。
制度の語りを昇華させる市民的主体が、制度の未来を担うのです。
制度を語るとは、
制度を生きること。
制度を育てるとは、制度に責任を持つこと。
そうした市民的実践が、
制度の暴力に対する最も強い防衛となります。
制度の語りを昇華させる市民的主体とは、
制度の設計思想に倫理を持ち込み、
制度の運用に責任を伴わせる存在です。
制度の語りを問い直し、再定義し、公共性を回復する語り手こそが、
制度の未来を担うのです。
そして今、制度の語りが暴力として機能する時代において、
私たちはその語りに介入する覚悟を問われています。
制度の言葉を誰が握るのか
──その問いを、私たち自身が引き受ける時代が始まっています。
制度は、誰かが作ったものではなく、
私たちが語り、
問い、
育てるものです。
制度の語りに市民が介入することで、
制度は支配装置から公共財へと変容します。
その営みは、単なる批判でも、
一過性の抗議でもありません。
制度の語りを継続的に問い直し、
倫理的に再定義し、公共性を帯びさせること。
それこそが、制度の暴力から社会を守る市民的防衛であり、
制度の未来を担う語りの実践です。
次回は、
「制度の語りが公共性を回復するとき──市民と制度の協働構造」
について掘り下げていきます。
制度の語りが市民の言葉と交差するとき、
制度は支配装置から共創の器へと変わります。
制度の言葉を誰が握るのか──その問いを、
私たち自身が引き受ける時代が、いま始まっています。