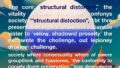こんにちは、\イッカクです/
30年も放ったらかしになってる
日本の政治・経済の停滞の真相についての
論考シリーズ、今回はの第3回目を以下置きます。
1990年代にバブルが崩壊し、日本は大きなショックを受けました。
けれど、そこで立ち上がれなかった原因は “ひとつ” ではありません。
表向きは経済の問題に見えますが、その裏側には、
政治、企業文化、価値観の変化、
そして時代の流れに対して日本がどう対応したか
――複数の要素が絡み合っています。
今回は、日本が“回復できなかった理由”を、
なるべくやさしく、順番に整理していきます。
■ 1. 政府の対応が「対症療法」だった
バブル崩壊後、政府はたしかに多くの政策を打ち出しました。
公共事業、金融緩和、税制の見直し……。
見た目には「やっている感」がありました。
しかし、問題は“根っこ”に触れなかったことです。
・企業の賃金が上がらない
・雇用が不安定化していた
・若い世代が将来を描きにくくなっていた
こうした生活の基盤部分はほとんど改善されないまま、
“表面だけ”を整える政策が続きました。
結果として、庶民の生活は軽くならず、消費は拡大せず、
景気は温まらない――。
これが長く続く土台になってしまったのです。
■ 2. 企業が「短期の数字」に縛られた
2000年代に入る頃、日本企業の価値観が大きく変わりました。
かつての日本には、
「会社は社員と共に育つ」
「良いものを作り続ければ必ず評価される」
という文化がありました。
ところが、グローバル化の波が押し寄せ、
“株主の評価”が企業の最優先事項になりました。
その結果、
・賃金よりも内部留保の積み上げが優先され
・未来の投資よりも、今期の数字が重視され
・社員よりも株主を見る経営が増えた
企業は確かに利益を出しました。
株価も回復しました。
けれど――
そこで働く人の生活は、豊かにならなかった。
日本の“回復できなさ”は、
この「利益は出るのに、生活は良くならない」という構図
そのものに表れています。
■ 3. 雇用の分断が、未来の力を弱めた
あなたも現場で体感されたように、
2000年代前半、正社員と派遣の間に“見えない壁”が生まれました。
仕事は同じでも待遇が違い、
現場では心の分断が起き、
チームの一体感が徐々に失われていきました。
しかも重要なのは、
技術やノウハウの継承が進まなくなった ことです。
日本企業の強みだった「現場で育てる文化」が弱まり、
経験が蓄積しない組織が増えました。
・人が育たない
・技術が継承されない
・危機に強い現場が作れない
これは10年や20年では取り戻せない傷です。
■ 4. 「日本らしさ」を手放してしまった
2000年代には「ISO規格」の導入が進みました。
もちろん良い面もあります。
しかし、日本にはもともと
“カイゼン文化”
“少集団活動”
“職人の美意識”
といった、世界でも類を見ない現場力がありました。
ところが、多くの企業は、
“現場文化”より“規格準拠”を優先する方向に流れました。
書類やルールが増え、
仕事はきれいに見えるようになった代わりに、
「現場で育つ強さ」が弱くなっていったのです。
それはちょうど、
“魂の入ったものづくり”が、
“書類で決められた作業”に置き換わっていった瞬間でした。
■ 5. ではなぜ、失われた文化を取り戻せなかったのか?
理由はシンプルなのに深い。
現場の文化は、作るのに時間がかかるが、壊れるのは一瞬だからです。
さらに、
・経験者が定年で抜けた
・若い世代が長く働けない
・企業が研修に投資しなくなった
こうして、日本を支えた“暗黙知の蓄積”が薄れていきました。
これは、数字には出ないけれど、
日本が回復できない最大のポイントのひとつです。
■ 6. そして30年後の今――
表向きの数字は改善して見えます。
株価は上がり、企業の利益は伸び、内部留保は過去最高。
——なのに、私たちの生活は変わらない。
その理由は単純です。
回復したのは“企業の財務”であって、
“日本社会の土台”ではなかったから。
・企業文化が変わり
・政治が生活を支えず
・現場の力が弱まり
・技術と経験が継承されず
これらが積み重なって、
日本は「本当の意味で」回復するタイミングを逃してきました。
■ おわりに
第3章では、「なぜ日本が立ち直れなかったのか」を、
できるだけ生活者の視点で追いました。
次の第4章では、
“では日本はどこから立て直せるのか?”
というテーマに移っていきます。
失われた30年は、決して宿命ではありません。
どこで間違えたかが分かれば、
どこから回復できるかも見えてきます。