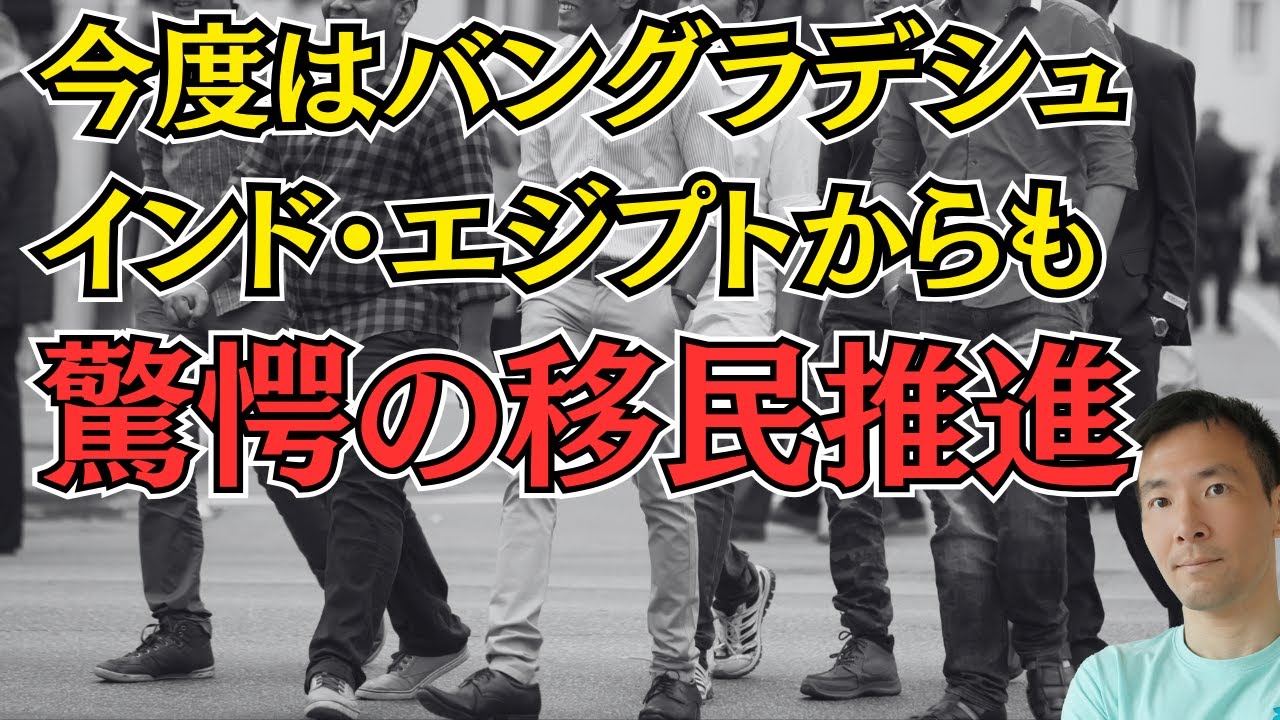第3章:制度戦の三層構造
──語り・設計・運用の非対称性
本章では、制度がどのように侵食されるかを
「情報戦・制度戦・文化戦」という三層構造で分析する。
ただし、制度そのものは
「語り・設計・運用」という三つの層で構成されており、
これらは制度の内在的な構造である。
一方、情報・制度・文化の三戦は、
制度を外部から操作・歪曲する戦略的メカニズムである。
本章ではこの二つの構造を明確に区別しながら、
制度の侵食プロセスを検証していく。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
あなたは最近、こんなニュースを目にしていませんか?
「バングラデシュから10万人」
「インドから50万人」──移民受け入れの話が、
まるで既定路線のように報じられています。
でも、ちょっと待ってください。
いつ、誰が、どこでそんな重大な決定をしたのでしょうか。
あなたはその議論に参加できましたか?
制度というのは、
語り・設計・運用という三つの層で構成されています。
そしてそのすべてにおいて、
私たち市民は
「外側」に置かれていませんか?。
制度は私たちの生活に深く関わるのに、
私たちはその中身に触れることすらできない
──それが、制度戦の本質なのです。
■語りの層──「善意」の制度言語による認知戦
まずは語りの層から見てみましょう。
制度はいつも
「人材育成」
「国際協力」
「多文化共生」といった、
耳触りの良い言葉で語られます。
いわゆる、ポリティカル・コレクトネス(ポリコレ)ですね。
最近のバングラデシュとの覚書もそうでした。
「日本の労働市場基準の遵守」
「技術スキル開発の相互協力」
──まるで未来志向の善意の制度のように聞こえます。
でも、
その語りの裏側には何があるのでしょうか?。
ある動画では、こうした語りが
「文化の衝突を無視した幻想」だと指摘されていました。
異なる文化を無理に混ぜれば、
当然摩擦が起きる。
それなのに、
制度はその摩擦を「共生」という言葉で包み隠すのです。
あなたが「それは良いことだ」と思った瞬間、
制度の語りは成功しています。
でも、その「良さ」は誰の視点から語られているのか
──そこにこそ、問いを差し込む余地があるのです。
■設計の層──市民不在の制度構築と利権の集中
次に設計の層を見てみましょう。
制度はどのように設計されるのか
──その過程は、私たちには見えません。
バングラデシュとの協定は、
現地紙「ダッカ・トリビューン」で報道されるまで、
日本国内ではほとんど知られていませんでした。
インドとの「50万人交流計画」も、
首脳会談で合意されるまで
市民には情報が届かない。
東京都とエジプトの覚書も、
都議会議員がSNSで確認するまで、
法的根拠すら曖昧だったのです。
制度設計は、
政府・企業・国際機関などの
利害関係者の間で密かに進められます。
市民はその過程に関与できず、
完成された制度が「説明」されるだけ。
でも、説明は参加ではありません。
それは、既成事実への服従を促す儀式にすぎないのです。
あなたが制度の「説明」を受けたとき、
それはすでに決定された事実です。
その瞬間、
あなたの意思は制度の外に置かれているのです。
■運用の層──制度の現場化とビジネス化
そして最後に、運用の層です。
制度が現場に降りてくると、
そこにはビジネスが生まれます。
ある動画では、
日本バングラディッシュ合弁会社、
ドリームストリート、
バングラジョブ訓練センターなど、
聞き慣れない企業名が次々と登場しました。
これらは、制度の運用段階で利権を得る構造の一端を示しています。
研修、認証、派遣、雇用
──制度の語りに沿ったサービスが展開されますが、
その実態は、制度によって生まれた市場の囲い込みです。
移民ビジネスはその典型であり、
制度が新たな経済圏を創出する手段となっているのです。
あなたはこの現場においても、
制度の受益者ではありません。
制度の影響を受ける「環境」として扱われるだけ。
制度はあなたの生活を再編しますが、
あなたの意思はそこに反映されないのです。
■結語──制度戦における市民の位置
語り・設計・運用
──この三層構造の中で、あなたは常に「外側」に置かれています。
制度はあなたのためにあると語られながらも、
あなたは制度の構築にも運用にも関与できない。
制度の語りに
従属する存在として位置づけられているのです。
でも、だからこそ、
あなたにはできることがあります。
1.語りを疑うこと。
2.設計の透明性を求めること。
3.運用の実態を検証すること。
制度に対して問いを発するとき、
制度戦は始まるのです。
それは、倫理的抵抗の第一歩。
市民による制度の再定義。
あなたの問いが、
制度の構造を揺るがす力になるのです。
立ち上がりましょう、日本人!👍️