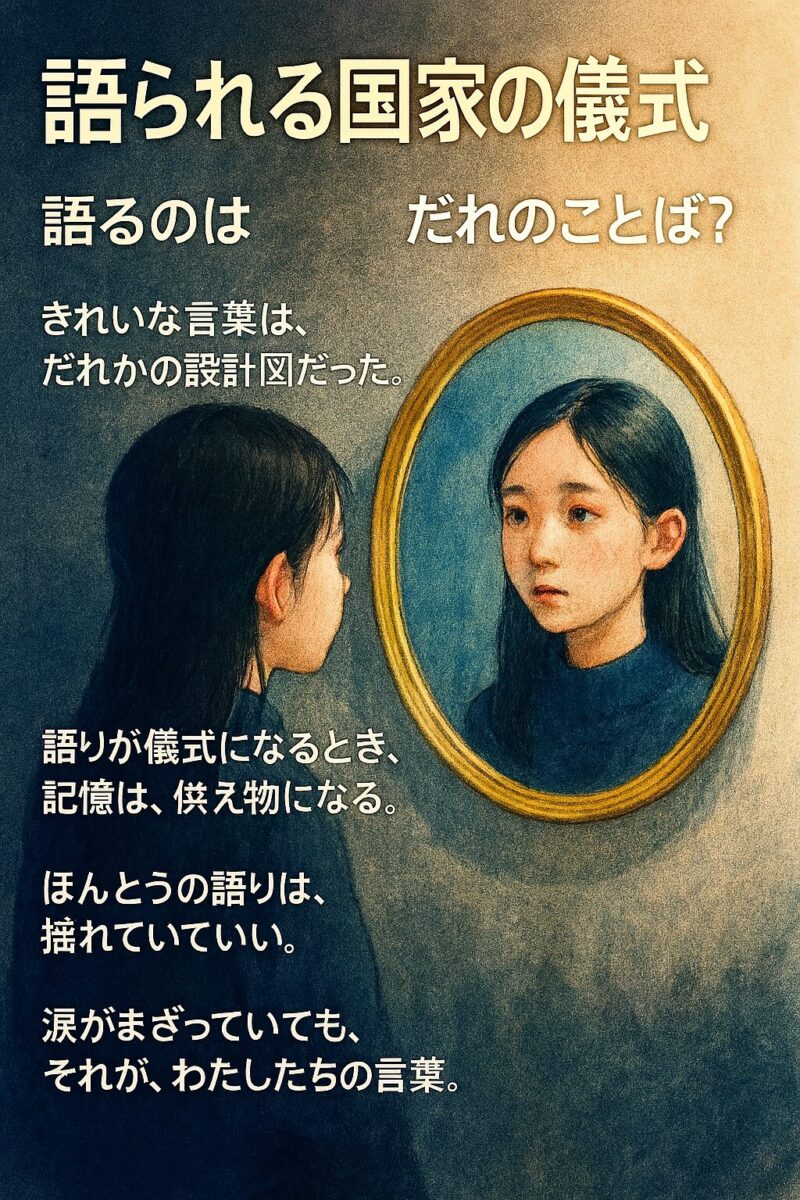こんにちは、\イッカクです/
今回は、「語られる国家の儀式」論考シリーズの3回目。
第3章 語りの鏡像
──制度語彙と実態の乖離を見抜く技法
語りは、祈りではない。
でも、誰かの設計図をなぞるとき、 それは儀式になる。
きれいな語彙が並ぶとき、 語り手の揺らぎは消える。
聞き手は、語られない者となり、 記憶は、供出される。
国家は語る。 でも、それは誰の言葉だろう?
──ほんとうのことは、どこにある?
1. きれいな言葉に、だまされないで
ニュースや会見で、政治家が話す言葉って、
なんだか難しく感じませんか?
「民間活力を活かす」
「持続可能な運営」
「県民の負担軽減」
── いかにも良さそうな言葉。
でも、これって本当に意味があるの?
というか、具体的にどうするの?
じつは、こういう言葉は
「語彙(ごい)」と呼ばれるもので、
そのままでは中身がよくわからないことが多いんです。
まるで魔法の呪文みたいに、
くり返されるだけで、説明はされない。
そして、その言葉を誰が作ったのかを調べてみると
── 日本の政治家ではなく、
外国の企業や研究所が使っている言葉だったりします。
つまり、政治家は「自分の言葉」で話しているようで、
実は「誰かが作った言葉」を
借りて来て使っているだけかもしれないのです。
2. 宮城県の水道の話
たとえば、わたし住む宮城県では、
水道の運営を民間の会社に任せるしくみが始まってます。
これを「PFI(ピーエフアイ)」といいます。
県はこう言いました:
「民間の力を使って、県民の負担を減らします」
「水道を長く安定して続けられるようにします」
「地元の仕事も守ります」
でも、実際に調べてみると
── 水道を運営する会社には
「ヴェオリア」というフランスの企業が関わっています。
日本の会社に見えても、
じつは外国の会社が出資していて、
その会社が水道の料金や利益を決める力を持っているんです。
契約は20年間。
とても長いですよね。
その間、県民はその会社の決めたしくみに
従うことになります。
そして、「地元の仕事を守る」と言っていたのに、
実際には、地元の会社の仕事が減ったり、
働く人がパートや契約社員になってしまう
ケースもあると報道されています。
3. わかりやすく話せない人は、責任を取るべき
政治家や公務員は、
みんなの生活に関わることを決める人たちです。
だからこそ、「わかりやすく説明する責任」があります。
もし、むずかしい言葉ばかり使って、
「結局どうなるの?」が伝わらないなら
── その人は、説明する資格がないと言ってもいいかもしれません。
制度や契約のしくみを、
中学生にもわかるように話せること。
それが、本当に「語る力」だと思います。
参考資料リンク一覧(2025年10月時点)
宮城県公式情報・契約構造
運営会社と資本構造
4. ほんとうの語りを、取り戻そう
言葉は、ただ並べるだけじゃ意味がありません。
その言葉に、記憶や気持ちがこもっているとき、
はじめて「語り」になります。
政治の語りが、
誰かの作った言葉をくり返すだけなら、
それは「語り」じゃなくて「命令」になってしまいます。
だからこそ、私たちは「語りの鏡」を持たなければなりません。
きれいな言葉の裏にある、本当のしくみを見抜く力。
そして、自分の言葉で語る力。
それが、未来を守るための「語りのちから」です。
わたしたちは、聞いていた。 でも、語られていなかった。
きれいな言葉は、 だれかの設計図だった。
語りが儀式になるとき、 記憶は、供え物になる。
ほんとうの語りは、 揺れていていい。
涙がまざっていても、 それが、わたしたちの言葉。
つづく。