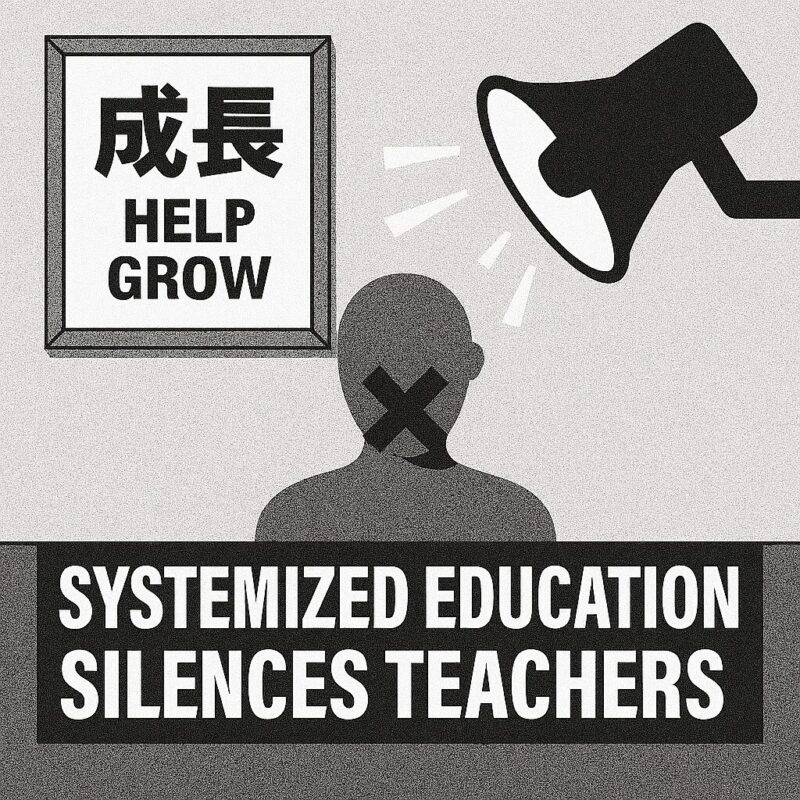こんにちは、\イッカクです/
今回は「理想が制度に変わると、
人間性を弾圧する」論考シリーズの2回目です。
第2章 教育現場の理念空洞化
──制度化と沈黙の強制
あなたが最後に「教育とは何か」と考えたのは、
いつだったでしょうか。
子どものために、学びの自由を守るために、
教師は日々現場で判断を重ねています。
けれど、その判断は制度の中でどれほど尊重されているでしょうか。
この章では、教育現場において理想が制度に吸収され、
沈黙が強制される構造を見ていきます。
教育には、理想があります。
「子どもの可能性を伸ばす」
「個性を尊重する」
「学びの自由を守る」
──それらは、教育者の誇りであり、
社会の希望でもあります。
教員養成課程では、こうした理念が繰り返し語られます。
教育委員会の資料にも、学校のパンフレットにも、
理想は掲げられています。
けれど、現場に立った瞬間、
教師は気づきます。
その理想は、制度の中で空洞化しているのです。
たとえば、
ある公立学校では
「生徒の個性を尊重する教育」が理念として掲げられていました。
しかし、実際には、授業進度は学年ごとに統一され、
教材は指定され、
評価基準は数値化されていました。
教師が独自の判断で教材を変更しようとすると、
「指導要領に反する」として制止される。
生徒の個性に合わせた指導を試みると、
「公平性に欠ける」として否定される。
理想は制度に吸収され、制度は管理の道具となっていたのです。
制度は、理想を形式化するとともに形骸化します。
「自由な教育」は「標準化された教育」に変わり、
「教師の裁量」は「管理職の承認」に置き換えられる。
そして、制度は沈黙を強制します。
教師が声を上げようとすると、
「組織の秩序を乱す」として排除される。
教育現場では、理念が制度に吸収されることで、
語られない教育、記録されない判断、沈黙する教師が
生まれていくのです。
この構造は、数字にも表れています。
文部科学省の調査によれば、
教員の在校時間は週50時間を超えることが多く、
部活動、保護者対応、校務分掌、地域行事などが業務を圧迫しています。
しかし、これらの業務の多くは記録に残らない。
「働いているのに、働いていないことになる」
──そんな矛盾が、教育現場には日常的に存在しています。
さらに、教員不足の問題も深刻です。
令和7年度の教員採用倍率は過去最低を記録し、
管理職が担任を兼任する事態も発生しています。
制度の限界を訴えても、
代替人材が確保できないため、
声を上げることが「迷惑行為」とされ、
沈黙を強いられる。
制度は、理想を掲げながら、
現場の声を排除する構造を強化しているのです。
あなたがもし教育者なら、
こうした構造に心当たりがあるかもしれません。
「子どものために」と思って行動したことが、
制度の中で否定された経験。
「このままではいけない」と感じたのに、
声を上げられなかった記憶。
それは、あなたのせいではありません。
それは、制度が理想を吸収し、
声を排除する構造の中で起きたことなのです。
この構造は、教育に限りません。
労働、政治、医療──あらゆる制度において、
理想が制度に吸収されるとき、
現場の人間性は抑圧されます。
制度は理念を掲げながら、
実際には沈黙を強いる。
そして、形式だけが残り、声は消えていく。
では、教育はどうあるべきなのでしょうか。
制度を否定することではありません。
教育制度は必要です。
学習指導要領も、
評価基準も、
学校運営も、
社会には不可欠です。
問題は、制度が理想を吸収したときに、
教師の声を記録する構造を持っているかどうかです。
制度が、逸脱や異議申し立てを記録し、
検討し、再設計する構造を持っていれば、
教育は人間に戻ることができます。
制度が、記録されない判断を記録し、
語られない教育を受け止める構造を持っていれば、
沈黙は語り直されるのです。
この章では、教育現場における制度化の実態と、
それが教師の自由と尊厳をどのように損なうかを検証しました。
また、教育現場では、「いじめ」との関連も深いです。
それについては。後続の章で書きます。
次章では、「改革」という理想が制度に吸収され、
反抗が制度の一部として無力化される構造を考察します。
そこでもまた、
制度が理想を掲げながら、
声を消していく構造が現れるでしょう。
そして、私たちは問い続けることになります
──制度は、声を記録する構造を持っているか?と。