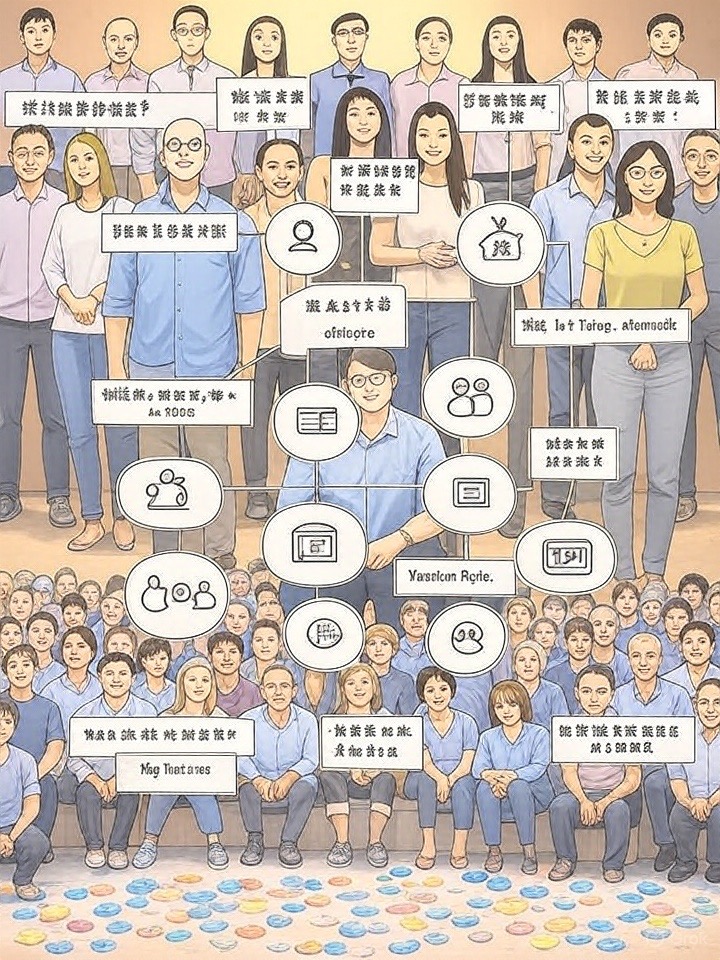第9章:制度の語りを再設計する技法
──移民制度を市民の手で描き直す
こんにちは、\イッカクです/
前回は、制度の語りを「手に取る」ための技法
──図解・言語・メタファー
──を見てきました。
でも、制度を読み解くだけでは足りません。
今回は、制度そのものを描き直す技法に踏み込みます。
そして今、
私たちの社会で最も制度の再設計が求められている領域
──それが「移民制度」です。
「移民問題」とは誰の問題か?
ニュースでは「移民問題が深刻化」と報じられます。
でも、ちょっと立ち止まって考えてみませんか?
誰が「問題」だと言っているでしょうか。
誰にとって「問題」なのか。
そして、誰がその制度を設計しているのか。
制度の語りは、しばしば行政や専門家の言葉で語られます。
「文化的適応力」
「地域との共生」
「制度的整合性」── でも、そこに市民の声はあるでしょうか?
制度の構造を描き直す──入国審査の例から
たとえば、入国審査。
「郷に入っては郷に従え」という言葉が、
審査基準の裏に潜んでいます。
でも、それって誰が判断しているのでしょう?
文化的適応力とは何か?
地域との共生とは誰が決めるのか?
団体申請はなぜ制限されるのか?
このような問いを制度の構造に挿入することで、
制度の設計図を描き直すことができます。
図解してみると、こうなります:
申請者 → 入国審査官 → 審査基準(文化・言語・地域理解)
地域住民 → 意見反映の仕組み → 不在の合意形成
この構造に、市民の語りを挿入する余地はあるはずです。
言葉を編み直す──制度文言に市民語を挿入する
制度は言葉でできています。
だから、制度を描き直すには、言葉を編み直す必要があります。
たとえば、こんな制度文言があります:
「申請者は地域社会との文化的適応力を有することが望ましい」
これを市民語にすると、こうなります:
「その人が、地域の暮らし方にちゃんと合わせられるかどうかを見るってことです」
でも、ここで終わってはいけません。 市民の語りは、こう続きます:
「うちらの暮らしに関わるなら、ちゃんと話し合ってからにしてほしい」
「文化って、誰の文化?どこまで合わせればいいの?」
制度文言に、市民の問いを挿入する。
それが、制度設計の言語を描き直す技法です。
倫理を挿入する──制度設計に問いを刻む
制度は構造と語りでできています。
でも、それだけでは足りません。 制度には、倫理が必要です。
たとえば、こんな問いを設計図に刻むことができます:
誰が排除されるのか?
誰が説明を受けていないのか?
誰が責任を負っていないのか?
移民制度の設計に、
こうした問いを挿入することで、
制度は支配装置ではなく、社会の器へと変わります。
市民が制度を描き直すとは、どういうことか
制度を描き直すとは、社会のあり方を描き直すことです。
市民が制度設計に入ることで、
制度は生活の実感と倫理を帯びるようになります。
それは、制度を「誰かがつくるもの」から、
「私たちが語り、問い、育てるもの」へと変える営みです。
結び──移民制度の未来を、市民の手で
移民制度は、今まさに描き直されるべき制度です。
摩擦が起きているなら、
その原因を構造から問い直す。
制度文言が抽象的なら、市民語で編み直す。
倫理が欠けているなら、問いを挿入する。
制度の設計図を、市民の手に。
そのための技法を、これからも一緒に探っていきましょう。
次回は、
具体的な制度設計の実践編──水道事業や住宅制度などを
題材に、描き直しの技法を展開していきます。