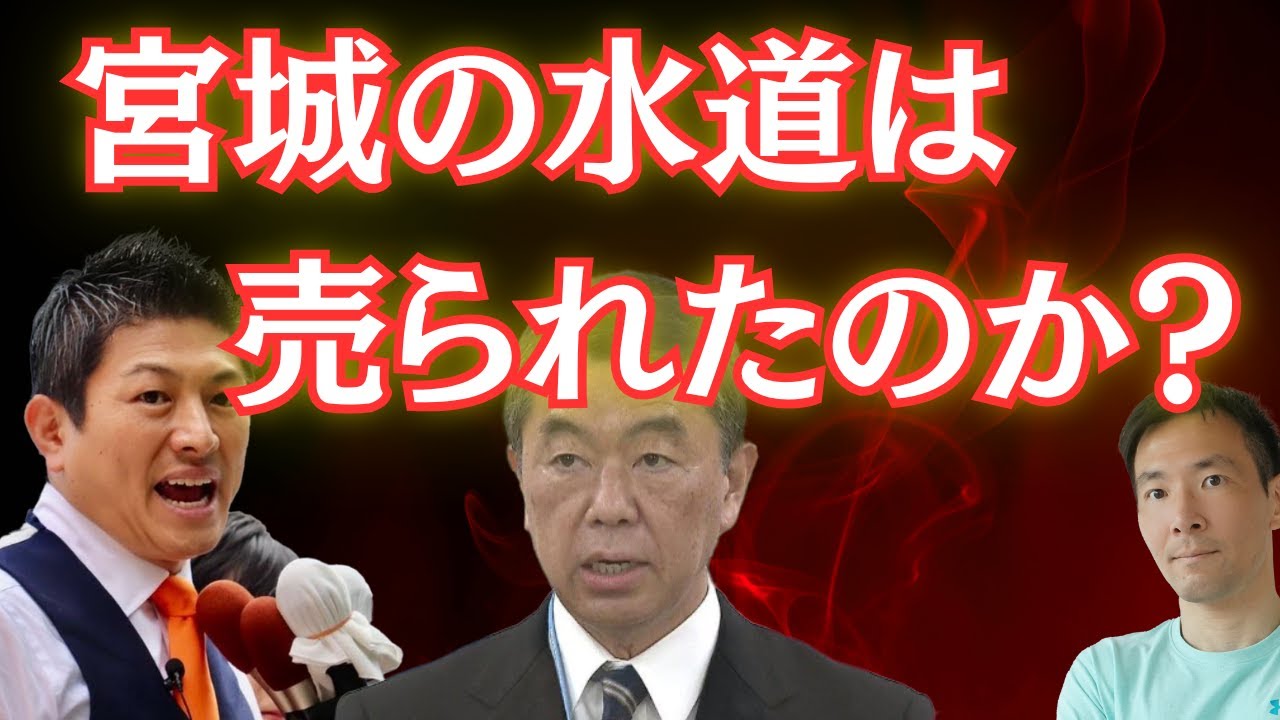水は命だ——誰もが理解しているはずのシンプルな事実が、
制度や契約の前では無力化される。
今回は、
宮城県が導入した「水道民営化」施策に関する一連の騒動について
公共インフラの扱い方に対する根本的な問題を炙り出している。
■編集後記
「宮城型管理運営方式」の実態と欺瞞
表向きは民営化ではないと言われる宮城県の水道事業。
施設の所有権は県が保持したまま、
運営権のみを民間企業に委託する「コンセッション方式」が採用された。
しかし、この契約構造は実に分かりにくく、そして巧妙だ。
運営権は「水結びマネジメント宮城」
という合同会社に売却されたが、
実際の運営は「水結びサービス宮城」が担当している。
契約会社と運営会社が別であることに加え、
後者の株主構成が非公開。
調査によれば、
外資系水メジャー企業ベオリアが議決権の過半数を持っているという。
自治体が契約しているのはマネジメント会社だけ。
つまり、実際のサービス運営に対する監督権が不透明で、
責任の所在も希薄になる。
これは行政の責任放棄であり、
統治を支える民主主義の根幹にかかわる問題だ。😱
民間が利益、自治体が赤字を背負う構造
さらに問題なのは、
この仕組みが民間の利益を優先する構造になっている点だ。
資材調達や薬品供給、設備更新など収益が見込める業務は民間へ、
莫大な維持費がかかる水道管の管理は引き続き県が担当する。
つまり、コストを伴う部分は自治体が引き受け、
利益を生む部分だけ民間が担う。
この“民営化”は、
企業にとってはリスクゼロの金のなる木。
公共インフラとは呼べない構図だ。
水道料金が高騰する理由とは
この構造の影響か、
宮城県は全国水道料金ランキングで第3位。
寒冷地や人口密度の影響があるとはいえ、
より寒い岩手や秋田より高い料金設定には違和感しかない。
節水が進むことで水道の使用量が減り、
それが経営悪化につながるという矛盾も深刻だ。
水を節約することが善とされながら、
節水が自治体の財政を苦しめる。
この制度的バグは本質的な設計ミスだ。
巨大企業の侵入と民主主義の危機
水メジャー企業ベオリアは世界最大の水道企業であり、
その資金力と政治力で
世界中の水道事業に介入している。
石油、穀物、そして水
——生活に不可欠な資源ほど、巨大資本による支配が加速していく。
オカシクないですか?
資金力が競争力になり、
政治力が制度に介入する。
地方自治体が企業の影響力に抗えなくなったとき、
民主主義の原則は崩れ始める。
インフラは国家の責任であるべき
日本のインフラは高度経済成長期、
国が財政を投じて築いてきた。
その更新期に入った今、
「水道経営が厳しいから民間に委託」
「料金値上げで負担を国民に」
という発想は、国家の役割を忘れた怠慢である。ということです。
外資による“コスト削減”の実態は、
日本人の給料を削るだけ。
国内でお金を回す仕組みを維持するためにも、インフラは潔く税金で守るべきだ。
地方インフラは「切り捨て」ではなく「再生」の鍵
「人口が減る地方はインフラを縮小すればいい」という声もあるが、
発想は逆だ。
交通や生活インフラがあるからこそ産業が生まれ、
人が住み始める。
東京の過密を補完するポテンシャルは地方にこそある。
だからこそ今、
国が責任を持って地方インフラに財政を投じるべきなのだ。
水道の民営化に見える構造的問題は、
日本全体の未来に直結している。
では、また。