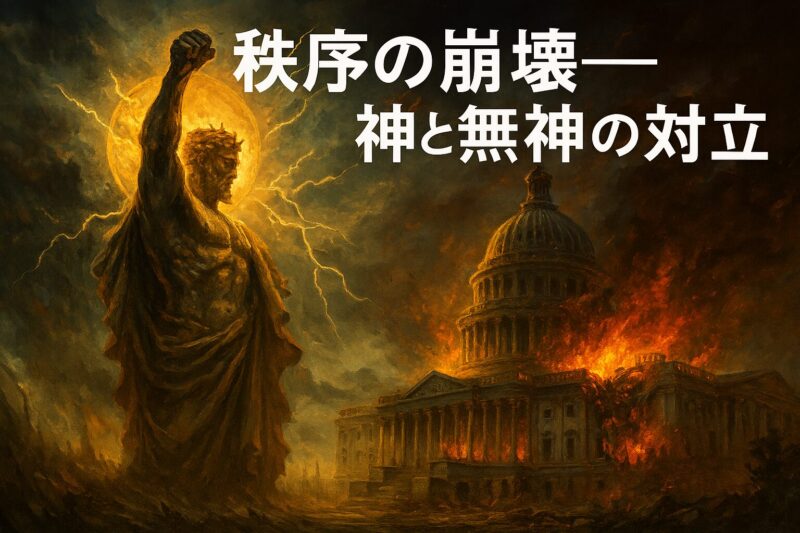こんにちは、\イッカクです/
今回から、シリーズ
「 信じるもの・守るもの・祈るもの」を語ります。
では、、、
あなたは、政治を語るとき、
宗教や思想のことを思い浮かべますか?
それとも、制度や法律、経済の話だと思っているでしょうか。
多くの人は、政治と宗教は
「分けて考えるべきもの」だと教えられてきました。
それは、学校でも、メディアでも、
憲法の条文でも、繰り返し語られてきたことです。
「政教分離」
──その言葉は、まるで常識のように扱われています。
けれど、現実の世界を見渡してみてください。
米国では、福音派が政治の中枢に入り、
選挙を左右していますよね。
イスラム圏では、
宗教法が国家の骨格を形成しています。
中国では、宗教を排除し、
唯物論という思想体系が国家の正統性を支えています。
つまり、
政治とは思想の実践であり、
宗教とは秩序の根拠なのです。
それを庶民に悟らせまいとするために、
あえて「政教分離」という制度が強調されているのかもしれません。
本当は、分離されていない。
むしろ、深く結びついている。
それが、現代の地政学の本質です。
政教分離という幻想──ロシアという事例
あなたは、「政教分離」という言葉を信じていますか?
政治と宗教は分けられる──そう教えられてきたかもしれません。
けれど、現代の地政学を見渡すと、
その前提が揺らいでいることに気づきます。
たとえば、ロシア。
プーチン政権の背後には、ロシア正教会が静かに、
しかし確かに張り付いています。
教会は単なる宗教施設ではなく、
国家のアイデンティティを支える柱となっていますね。
プーチンは、ロシア正教の祝福を受けながら、
「聖なるロシア」
「道徳的な使命」
「西洋への霊的抵抗」
といった言葉を用いて、
政治的行動に宗教的正統性を与えているのです。
これは、単なる信仰の問題ではありません。
ロシア正教は、国家の歴史的記憶と結びつき、
帝政ロシアの栄光、ソ連崩壊後の再生、
そして現在の地政学的野心にまで影響を与えている。
教会は、国民の精神的秩序を支えながら、
政治の語彙に「神聖」「犠牲」「救済」といった宗教的意味を
染み込ませているのです。
つまり、プーチンの政治は、
宗教的秩序と国家的秩序が融合した構造なのです。
それは、政教分離という制度的原則を超えて、
「秩序の正統性」を宗教に根ざす試みでもあります。
この事例は、世界の他の地域とも響き合います。 米国の福音派、イスラムのシャリーア、中国の唯物論、そして日本神道── それぞれが、
政治の奥底に宗教的・思想的秩序を抱えている。
だからこそ、私たちは問い直さなければなりません。
政治とは何か?
それは、制度の話ではなく、
人々が何を信じ、何を守り、何に祈るかという
秩序の話なのです。
このシリーズでは、そうした「見えない構造」を見つめていきます。
世界の秩序は、宗教と思想によって形づくられ、
その衝突と再編が、私たちの未来を決めていく。
だからこそ、まず問い直してみましょう。
あなたが「政治」と呼んでいるものは、
本当に制度だけの話でしょうか?
その奥にある、信じるもの・守るもの・祈るものを、
見落としてはいないでしょうか?
──それが、秩序の転回を読み解く第一歩です。
かつて、世界には「ひとつの秩序」があると信じられていました。
神の名のもとに築かれた秩序
──それはカトリック的な中心であり、
欧米の価値観が「普遍」とされ、
世界を包み込もうとしていたのです。
教皇の言葉が道徳の基準となり、
ラテン語の祈りが文明の礎となり、
「神の代理人」が政治と宗教を結びつけていた。
それは、秩序の名のもとに整えられた世界でした。
けれど今、
私たちはその秩序の終わりを目の当たりにしています。
世界は静かに、
しかし確実に、多極化へと向かっています。
それぞれが異なる神を語り、
異なる正義を掲げ、異なる未来を描いている。
そしてその違いが、摩擦を生み、誤解を深め、
秩序そのものを揺るがしているのです。
米国では、福音派の「選ばれた国」思想が政治の中枢に入り込み、
神の意志を根拠にした政策が、経済や外交にまで影響を与えています。
信仰が国家のアイデンティティと結びつき、
「神に選ばれた民」としての使命感が、
他者との対話を難しくしている。
イスラム圏では、
宗教法が社会の隅々まで浸透しています。
シャリーアは、生活の規範であると同時に、政治の原理でもある。
その秩序は、神の言葉に従うことを前提としており、
世俗的な法や民主主義とは、根本的に異なる構造を持っています。
仏教圏では、
慈悲と縁起が政治倫理に影響を与えています。
争いを避け、調和を重んじる姿勢は、
他の秩序と衝突することを避けようとしますが、
その静けさが、時に「主張の弱さ」と誤解されることもある。
そして、中国。
共産党は「神なき秩序」を築いています。
宗教は管理され、信仰は国家の枠内に収められる。
秩序の正統性は、神ではなく歴史と安定に求められ、
監視と成果によって社会が維持されている。
この構造は、宗教的秩序と無宗教的秩序の対立というよりも、
「超越的価値」vs「実証的安定」という根本的な世界観の衝突です。
神の啓示に従うか、歴史の成果に従うか。
魂を救うか、社会を制御するか。
その選択が、世界の分断を生んでいる。
そして、もうひとつの極
──日本神道。
天皇制と祭祀が重なり合い、政治と宗教が静かに結びついている。
古代イスラエルとの接点を指摘する声もあり、
神輿や儀礼の形式に、遠い記憶のような共通性が見出されている。
その秩序は、語られすぎることなく、しかし確かに根を張っている。
こうして、世界はそれぞれの秩序を守ろうとしながら、
互いに理解し合うことが難しくなっている。
「あなたの正しさは、私の正しさではない」
その言葉が、対話を閉ざし、壁を築いてしまう。
でも、私たちは本当に、理解し合えないのでしょうか?
摩擦の中に、何か共通するものはないのでしょうか?
誤解の奥に、同じ問いを抱えていることに気づけないのでしょうか?
この章では、秩序の崩壊を見つめました。
それは、終わりではなく、始まりかもしれません。
ひとつの秩序が崩れるとき、私たちは問い直すのです。
「秩序とは何か?」
「正しさとは誰のものか?」
「私たちは、どこへ向かうのか?」
その問いが、次の章へとつながっていきます。
そして、あなた自身の気づきへと。
つづく。